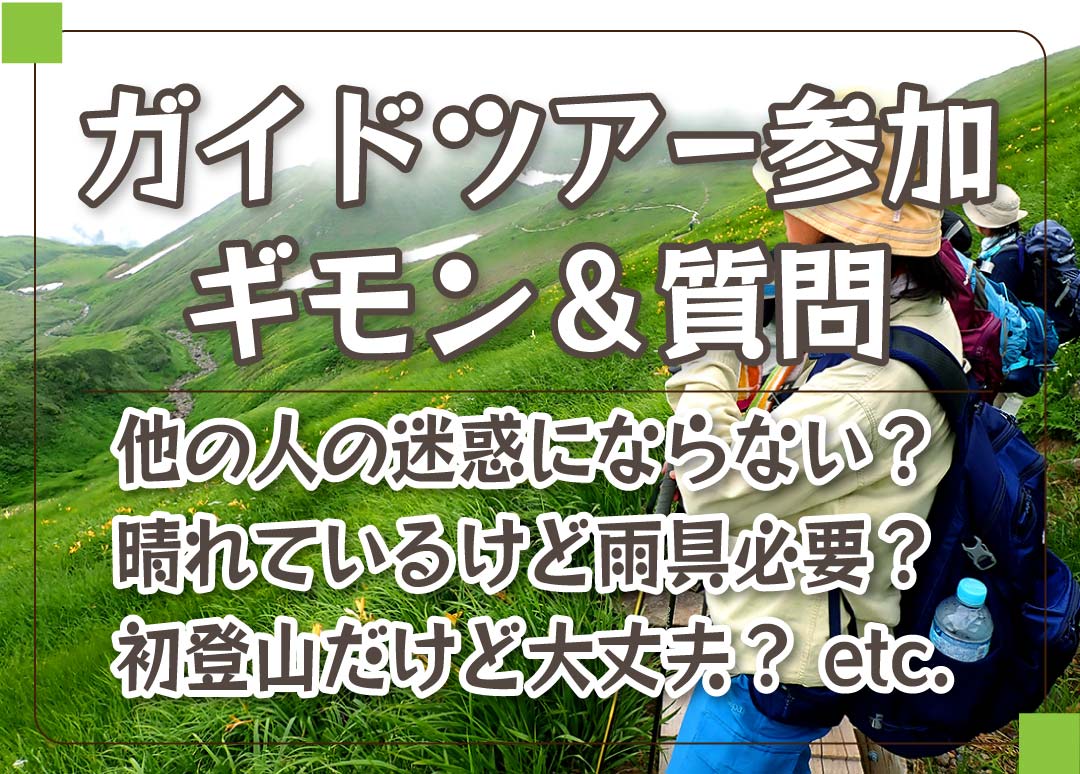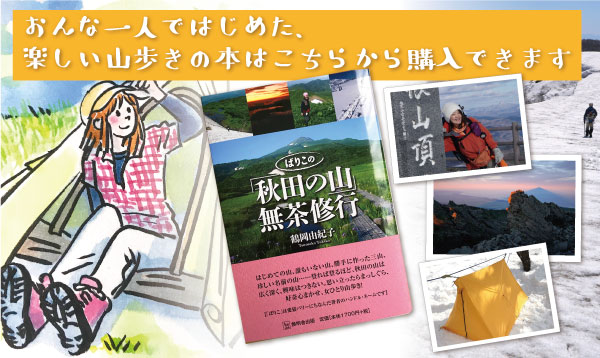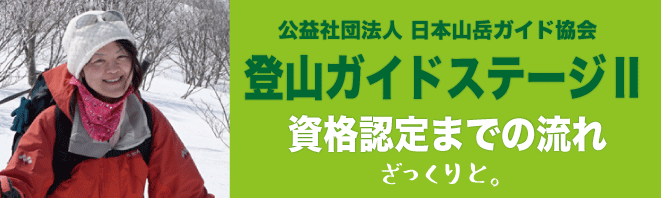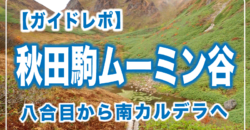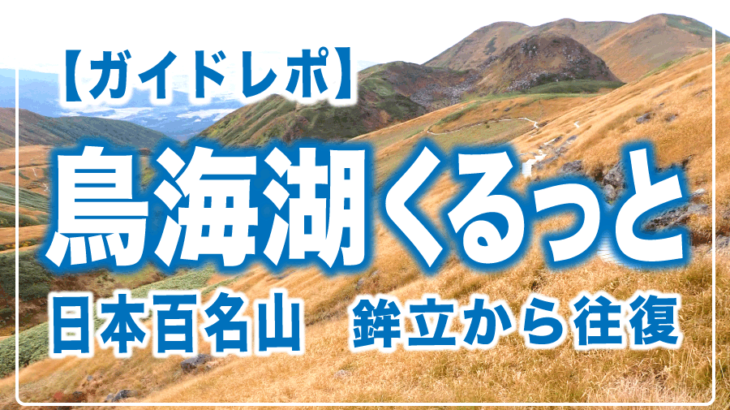月山は標高1984m、山形県の中央に位置する信仰の山。
湯殿山、羽黒山とともに出羽三山の一座でもある。
今年の6月、ちょうど山開きの日に
ガイド研修で姥沢口から登ったので、
こんどは八合目から
高層湿原を楽しみながら登りたいなと思っていた。
そう思っているうちにもう10月である。
そして八合目までの道路が
20日には冬季閉鎖されるという。
おりしもこの日曜はガイドを入れていない。
行かねば。
コースログはこちら
ガスの八合目登山口出発

ということで、横手を5時に出発し
8時前に八合目到着。
途中からガスが濃くなって、
そのせいか登山口方面から
山を諦めたのか降りてくる車何台かとすれ違う。
駐車場は空いていて
雨は降っていないが、ガスが濃く
そして空気はひんやりと冬を思わせる。

寒いし、ガスだしで
なんだかテンション下がる。
ここまでの道すがらの蕎麦屋で
温かい月山蕎麦でも食べてのんびりしたい気分しかない。

けどまあ、せっかくだし。
少し歩いてみるか。
駐車場からガスの中に木道がはじまる。
景色などほぼ見えず、
そして木道は濡れていてよく滑る。
湿原散策路を周回しているらしい
若人たちの、滑りまくる悲鳴が
ガスのなかからうるさい。
ますます帰りたくなりながらも
滑りやすい木道を進む。

分岐まで来ると、木道が終わって
石畳の登山道となる。
なんにも展望効かないし
滑る木道に神経すり減らしたし
もう帰ろうかと思うも、あの木道を
こんどは下りながら戻るというのは
考えるだけで気が滅入る。
山頂まで行って帰って来れば
木道も乾くだろうと、
そんな動機で登り始める晩秋の月山である。
仏生池小屋へ

湿原は木道で滑る人々で騒々しかったが
登山道がはじまると一転して静かである。
比較的ゆるやかな道である。
ずっと、石畳となっている。

きっと湿原が一望できるだろう開けた場所に出たようだが、相変わらずのガスの中である。

気温は5〜6度程度の予報だが
風があって、体感温度は氷点下に感じる。
動いていると暑いが、指先など冷える。
防寒テムレスを車に置いてきたことを
後悔しつつ、
どこかキリのいいところで引き返して
蕎麦を食べに行こうとズルズルと考えながら登る。

一ノ岳付近、やや斜度が出てきて
そこを登り切れば斜度がゆるむ。
平坦な道を進んでいると
ぬっと仏生池小屋に出た。
すでに営業は終了し、
トイレも雪囲いしてあって使えない。
営業中ならば、ここで
なにか温かいものでも口にして
下山に気持ちを切り替えるいいポイントなのだが
それも叶わないので先へ進む。

オモワシ山。
たしかあのガスのなかにあるはずの山の名だ。
もうここまで来れば
山頂まで1時間ぐらいだろう。
何も展望もないが、そうだな、山頂を踏めばヤマップのバッジがいくつか貰えるだろう。
そんな動機に気持ちを切り替えるイマドキの登山者。
月山山頂へ

ところがどうだろう。
なんと、ガスが上がっていく。
月山ならではの、広大な高層湿原が姿を現す。

行者返しをすぎてモックラ坂を登っていく。

ガスの下に見える展望に
足が進まなくなる。

山頂方面が近づいてきた。
もはや帰るという発想は霧散する。

狂い咲きのハクサンイチゲ。
寒そう。

霧氷があった様子。
寒いはずだ。

ガスがなければ展望のいいところ。
まだまだスッキリとは上がってくれない。

木道ふたたび。
だが、乾いている。

大峰が見えてきた。

山頂の小屋も見えてきた。
三角点は、小屋の手前にある。

彼方に蔵王連峰。

狂い咲きのアオノツガザクラ。

登山道から踏み跡をたどってひと登りで
10:55、月山山頂。
三角点は1979.5m。
ちなみに最高地点は神社のある方面で
ここより5mほど高い1984m。

山頂に立てば、360度の視界。
さすが三角点。
見渡す紅葉は終盤。

ここまでガスだった理由が解明する。
濃い雲海の底をずっと歩いていたのだ。
彼方には鳥海山。
山形方面からのその山容は
秋田県の横手界隈からのとはまるで違う。

柴灯森方面。

舟形連峰方面。
雲の切れ間に覗く山並みは
慣れない山域なので山座同定がすらすらできない。

六月にお世話になった山小屋は
もう営業終了。

トイレはバイオトイレは閉鎖され
男女兼用で冬用トイレ、
つまりいわゆるドッポンの和式が
開放されている。

月山神社。
実はまだ入ったことがなかった。
以前来た時は、
お金を持っていなかったので入れず、
6月の山開きのときは
神事が執り行われるので行列に
並んだものの、
時間がかかりすぎたのと
そもそも研修中だったので
途中リタイヤ。

シーズン外なので出入り自由だ。

神社をお参りして、さてお昼。

山頂、稜線は風が強くて寒かったが、
稜線の南にまわればほぼ無風。
この地形はありがたい。
草紅葉の草原を眺めながら、ひといき。
高層湿原と鳥海山展望しながら下山

とはいえ、寒い。下山しよう。
登りではまるで見えなかった景色が
すっかりあらわに。
ほんと、途中で帰らないでよかった。

雲海。

雲海のなか、ただひとつ鳥海山。
山形県からは新山のある東鳥海山と
御浜のある西鳥海山が見える。

月山の八合目から登る理由はこの広大な高層湿原。
散りばめられた池塘群のきらめきがアクセント。

せっかくなのでのんびり帰ろう。
シダやコケに足が止まる。
こちらはコスギラン。シダの仲間。

佛生池小屋が見えてくる。

小屋を過ぎれば、弥陀ケ原の池塘群が一望できる。

下山はずっと前方に鳥海山を眺めながら。

木道が出てきた。
思惑通り、すっかり乾いている。

乾いた木道なので
リラックスして景色を堪能できる。

あちらの建物は
月山中の宮、御田原参篭所。
大きな兎の像がある。
あの兎は狛犬ならぬ、狛兎なのだそうだ。
だがきょうは駐車場へこのまま向かう。
帰りの運転が長いので、ここまで来ればもう
早く帰りたくなってきた。

駐車場もすっかり視界クリアに。

こんな石碑があったのか。
朝日連峰の同定ができる。

駐車場からも鳥海山。

立派なトイレ。
帰り道、明日には冬季閉鎖される車道沿いで
ヤマブドウ目当てに木登りしているクマに遭遇。
慌ててするすると木から降りて
森へひっこんでいった。