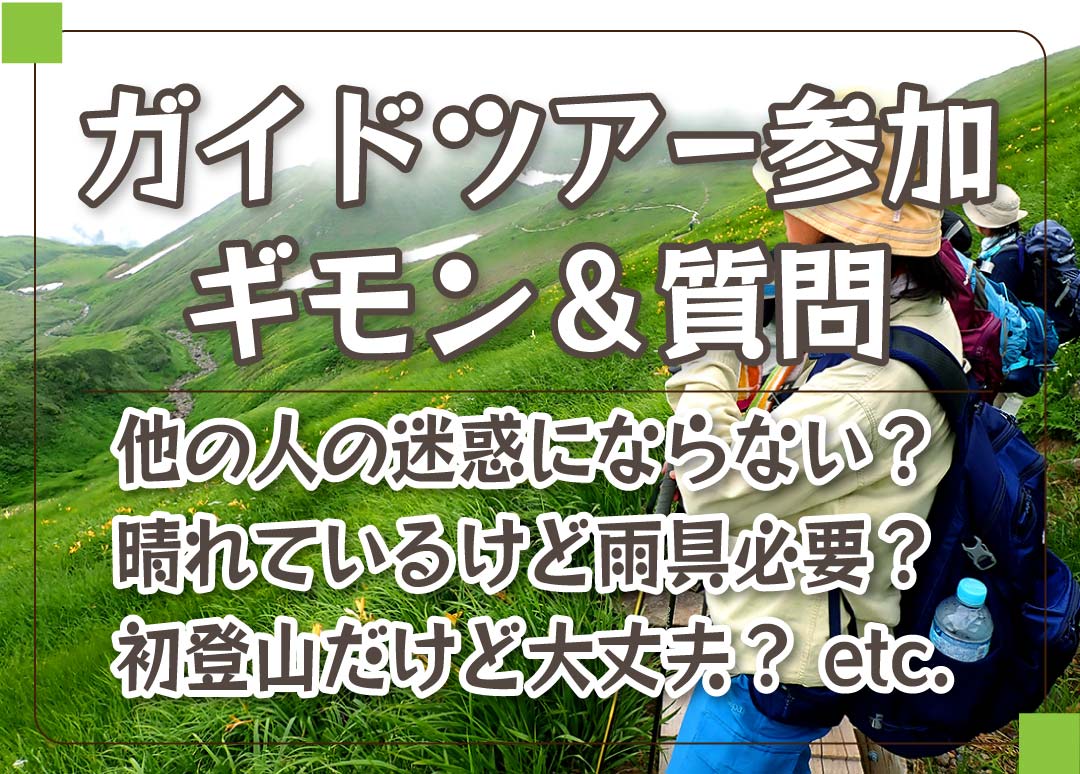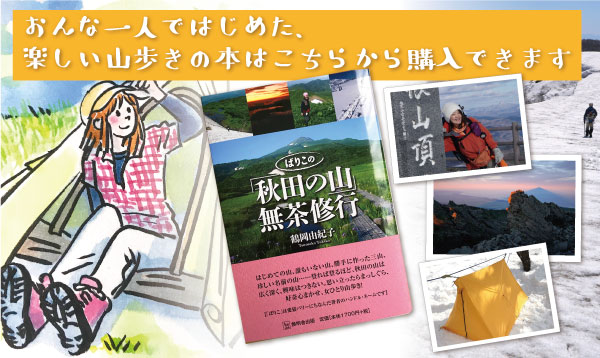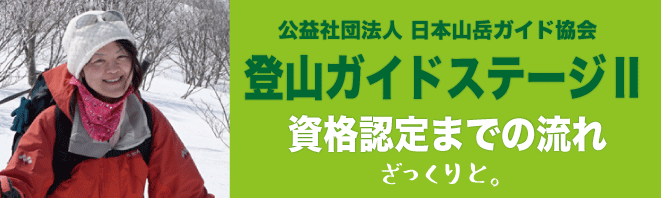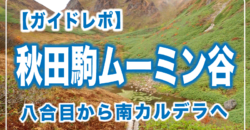鳥海山象潟コースの道迷いしやすい場所3つ
ブルーライン開通とともに
全国からの登山者で賑わう鳥海山鉾立口。
特に花のシーズンの連休は
多くの人で賑わうし、
登山道もかなりよく整備されているので
まさかこんなところで
道に迷うなんてと思いがち。
しかし残雪やガス、または疲労が原因で
道迷いしやすいポイントがある。
今回はその道迷いしやすいポイント3つを解説!
1、賽の河原

鉾立口から象潟コースを登り
一息いれるポイントでもあるのがここ。
腰を下ろすにもちょうどいい岩もあり
雪解け水の小川も流れ、
名前の割には気持ちのいい場所。
登山道も明瞭なので、道に迷う心配は
なさそうなのだが、
それは正規ルートを真面目に使っての話。
ここで言う正規ルートとは
地形図に記されている、御浜への登山道を示す。
しかし、この賽の河原から
笙ヶ岳方面の、長坂道丁字分岐への
ショートカットルートが
いつのまにかできてしまった。
たしかに、このショートカットルート、
10分ほど行けば大平コースと合流し
そのあとは立派な石畳の登山道となって
鳥海湖の外輪でもある、長坂道丁字分岐への
近道である。
この分岐からは、笙ヶ岳へ行くにも
鳥海湖を周回するにも便利なのである。
ところが、ほんの10分ほどのルートだが
ひとたびガスが出ると
踏み跡がとっても不明瞭なので
慣れない人は方向がわからなくなってしまう。
大平コースから賽の河原へ向かう場合も
どこからショートカットルートに入るのか
そんな標柱もない。
道迷いポイントは
次の地形図の丸で囲ったところ。

もし下山時に、このルートを見落として
石畳の立派な道をずんずん下山したとしたら
大平口に降り立つ。
大平口からはブルーラインを鉾立まで
3キロほどの道のりである。
なので、道がわからなくなった場合
いっそのこと、大平口へ降りてしまうのもいいかと思う。
2、外輪コースの湯ノ台道分岐

わたしも下山時に2回ほど間違えた箇所。
鳥海山の外輪コースの伏拝岳付近から、
御浜方面へ下山する外輪コースと
湯ノ台へ下山するコースが分岐する。
湯ノ台コース方面に入ると
あざみ坂と呼ばれる名の通り
アザミが多い坂となる。
もし下山時に伏拝岳をすぎて
アザミの多い、急な下り坂に入ったなら
それは道を間違えたことになるので
めんどうがらず、
正常性バイアスの罠を振り払って
登りかえそう。
外輪コースの場合、伏拝を過ぎたらまだ
外輪は続く。
そしてアザミの多い急な坂道はない。

3、7合目御浜と扇子森の間の岩場

①御浜小屋と扇子森の間
尾根上なので、道がわからなくても
深刻な道迷いにはならないが
タイムロスにはなってしまう。
御浜と扇子森の間の岩場で、
あまりペンキの印もなく
頼りになるのは、人が踏んだ跡でもある
泥のついた岩。
ガスのときや、暗いときなど
ほんと、わかりにくい場所だ。
もしガスや日没などでわかりにくいときは
コースは鳥海湖側よりに歩けば、ロープがはられている箇所がある。
慎重に、泥がついた岩を探して
ルートファイディングしよう。

②御浜小屋付近でコースが3つ分岐
御浜小屋までの登りはいいが、
下りの場合、ここでコースが3本分岐する。
鉾立に下りたければ、
下山時は御浜小屋の正面を通って
石畳のコースを下る。
大平方面へ下りたい場合は、
鳥海湖の外輪コースをとるか、
御浜小屋正面を過ぎて、
鉾立方面へのコースから分岐するところに
大平方面の標柱がある。
見落としそうな分岐だが、
標柱は新しいのでこれに注意して行けばよい。
大平口も鉾立口も
ブルーラインで繋がっているので
もし間違って下りたとしても
車道を3キロほど歩けばいいので
あまり慌てないように。
万が一道に迷ったら
迷わないことがいいとは
誰だってわかっているが
迷ってしまうときということは
どうしてもある。
万が一のため装備したいもの
1、ヘッドランプ
2、防寒着、
3、レインウエア上下
4、非常食
5、余裕を持った飲料計画
6、余裕をもった行動計画
7、登山届
8、スマホの予備バッテリー
9、事前の情報収集
どうやら道に迷ったときの心構え
あれ?おかしいなと
コースの違和感に気づいても
登り返す労力が惜しいときなどは
もう少し行ってみようと
ついついそのまま違和感を無視して
誤ったルートを突き進むことがある。
あるいは下山時刻が迫っている焦りから
引き返すよりも進む判断を
してしまうことがある。
山では「面倒くさがらないこと」が大事。
あれ?と気づいたら
まずは立ち止まる。
スマホで現在地を確認する。
じぶんが冷静じゃないときは
ついつい、スマホの調子が悪いかもと
正常性バイアスの罠にかかりがちだが、
そんなときは
たいてい、スマホとコンパスが正しい。
道迷い確定したときの行動
1、スマホ圏内なら下界と連絡を
2、明るいうちにヘッデンの準備
3、自力で下山できるならそうする
4、下山コース中、危険箇所がある場合はビバークの準備
5、危険箇所があるかどうかわからないならビバークの準備
6、ウエアを着込み、雨具も着込み低体温症予防。
7、夜明けを待つ。
以上、ざっくりとした説明ですが
道迷い遭難の怖いところは
焦って引き起こす二次遭難。
暗がりを進行して滑落や転倒、
冷えと疲労による低体温症など。
道迷いしないように
たとえ慣れたコースでも
余裕を持った行程と装備が大事。
優しげな景色の山に見えても
条件次第では牙をむく野生である。
ちなみに、
ビバークした人が地味に辛かったのが
虫だったという。
夏場は非常時のためにも
虫除け対策も忘れないようにしよう。