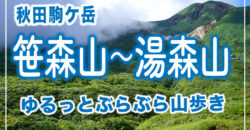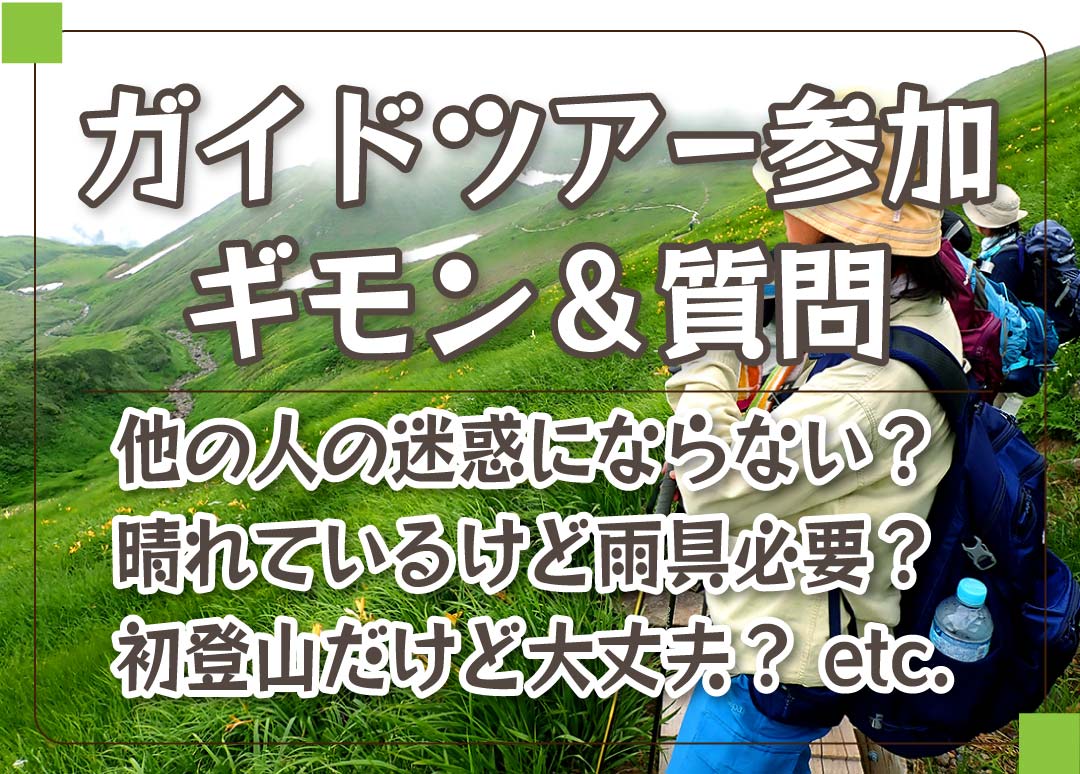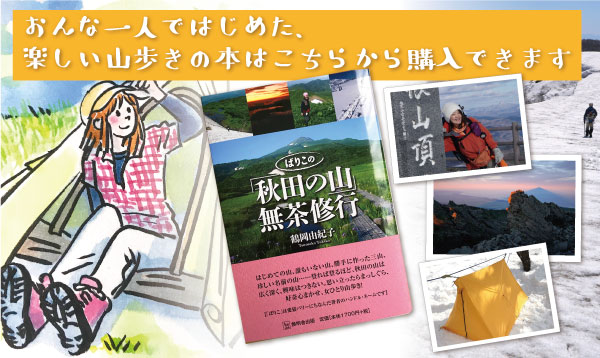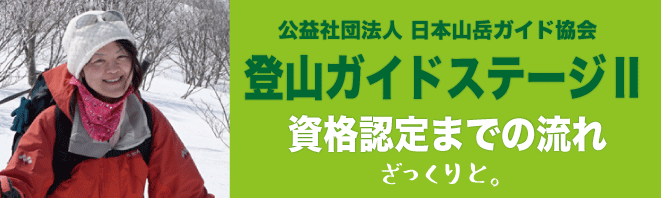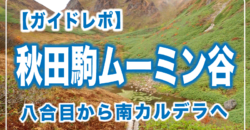和賀岳甘露水概要
コースタイム(往路)

| 歩行距離 | 登り累積標高 | 往路のみ所要時間(標準) |
| 15km | 1150m | 4時間15分 |
駐車場
↓15分
甘露水登山口
↓40分
滝倉
↓45分
倉方
↓35分
薬師岳
↓40分
小杉山
↓70分
和賀岳
アプローチ
登山口までの公共交通機関の運行はないので、クルマでの移動となる。
秋田自動車道を大曲ICから一般道へ。
みずほの里ロードを大神成方面へ進むと斉内川の河川敷に
大神成河川敷公園がある。
ここから斉内川沿いに真木林道を真木渓谷へ。
この林道をひたすら通行止めまで約8km進むとそこが登山口。
林道の状態は、普通車でも通行できるが林道なので狭いし、未舗装。
真木林道は大雨のあとなどは土砂崩れが起こりやすいので、事前に美郷町などに問い合わせることを
お勧めします。
甘露水口の登山口情報

駐車場
真木林道を一般車両通行止めゲートまで進むと、その道路脇が広くなっており、駐車場として利用できる。
ニッコウキスゲのシーズンになると、朝6時着ではすでに満車になっていることが多い。
この時期だけは駐車場確保が何よりの各心部だ。
ゲート前の駐車場が満車の場合、狭い林道脇には路駐車が延々と連なりはじめる。
駐車可能スペースはほかに、ゲート前から500mほど手前の小路又キャンプ場が利用できる。
キャンプ場と言っても、だだっ広い空き地があるだけで特に看板もないのでわかりにくいかも。
林道脇の広い空き地で、トイレらしき小さな建造物のある場所を目指そう。
ところで
以前は、甘露水口までクルマが入ることができてラクだった。
しかし登山口手前にある沢が、大雨のたびに土石流となって林道を破壊するものだから、ついに永遠に(?)通行止めとなってしまったようだ。
小屋とトイレ

一般車通行止めゲートのすぐ手前に、小屋がある。
登山ポストもこの小屋前にある。
このコース唯一の小屋であり、文明的なトイレもここだけだ。

小屋のは二階建てで、もちろん宿泊も可能。
電気水道のライフラインは通っていない。

トイレは男女兼用となるが、水洗トイレで和式1つに洋式が2つと充実している。
ペーパーも備え付けられている。
コース概要
駐車場から登山口まで

ここから約15分の林道歩きだ。
ついつい気が急いて、早歩きになる人もいるがこの先の行程も長いので、特に暑い日などはここで無駄に消耗しないよう、
特に中高年はゆっくり体を慣らすように歩くことををお勧めする。

標柱が現れて登山口であることに気づく。
甘露水の湧水が近くにあるので、たいていここは足元を水が流れている。

登山口の標柱から少し奥に、甘露水が湧き出ている。
冷たくておいしい、まさに甘露。
登山口から和賀岳へ
ブナ台まで

登山口から、うっそうとした印象の杉林の急登を登っていけば、森は明るい広葉樹林に入れ替わる。
ミズナラの巨木が出迎えて、目を楽しませてくれるゾーンだ。

登山道脇は、林床をシダが覆っていて圧巻なほど。
初夏には、ウリノキの小さな白い花なども見られる。

巨木とシダの森の山腹から、尾根に乗ったところがブナ台。
一息入れて周りをみわたせば、ブナの森が広がっていることに気づく。
滝倉まで

展望のない森の道ではあるが、ブナが優勢する豊かな森。
植物好きには興味がつきないゾーン。

こちらのブナ。
20年ほど前には「ブナ」と書かれたプレートの「ブ」の字が見えていたのだが、そろそろプレート自体も飲み込み完了しそう。

沢音が聞こえ始めると、傾斜が緩む。

尾根を少し下って、小沢を渡渉。
ここが滝倉だ。
とても冷たい水なので、夏場はここで涼が取れる。
このコース唯一の水場である。
倉方まで

滝倉から少し登ったところに滝倉避難小屋跡がある。
数年前まで転がっていた標柱も、すでに見当たらなくなった。
小屋が建っていた空き地もすでに草木が繁茂し、言われなければ気づかない。

急な山腹をジグザグに登って、やがて木の根っこをまたぐ巻道となって倉方だ。
倉方は風通りの良いブナの森の尾根。
蒸し暑い日もここまでくれば、ささやかな涼にほっとする。
標高も1000mを越え、ブナの樹高も低くなり空が近く感じ始める。
ここからのまっすぐな尾根道をしばし行けば、ようやく樹林の視界が開け真昼山地の深い山並みが見えてくる。
薬師岳へ!

ようやく視界が開け、見渡す山並みや遠く鳥海山の姿に歓声があがる。
とはいえ、登山道は尾根をやや東寄りにそれた山腹にあって、ところによっては露岩をへつるので、滑落には注意したい場所だ。
特に下草が繁る夏場などは、東側の急斜面への踏み外しには十分な注意を払いたい。

展望の良い日は、仙北平野を含む横手盆地とその彼方に鳥海山が見える。

右の急峻な頂を見れば、まだ急登が続くのかとため息が出る。
その隣の、まるい頂が薬師岳だ。

急登が緩むと、すずみ長根コースへの分岐。
すずみ長根コースは、定期的に刈り払いが行われるが、歩く人が比較的少ないせいか刈り払いから数年たつと藪道になりがち。
2025年は刈り払いが進められているようだ。
すずみ長根コースは、深い谷を見下ろしながら痩せ尾根歩きが楽しい素晴らしいコースだ。

薬師岳山頂。
山頂の手前には小さな祠がある。

山頂からは、目の前に和賀岳が裾野を広げる。
遠い、とため息を通り越して笑いが起こる。
薬師平界隈

和賀岳へのこのコース、ニッコウキスゲが人気である。
そのニッコウキスゲが最も濃いのが、薬師岳から薬師平へ向かう途中の稜線だ。
タイミングが合えば、薬師岳山頂から黄色く染まった尾根が見えるので、気持ちがはやる。
遠く、田沢湖の湖面。
さらに奥には森吉山も。

こりゃすごいわ。
当たり年の山腹。

薬師岳をバックにゴールデンコースを。
こうなると、和賀岳山頂などどうでもよくなってしまうので困る。

ニッコウキスゲゾーンを過ぎて、稜線をやや外れたところに薬師平。
笹薮の奥には小さな沼もある。

薬師平から稜線に上がって、小さなピークをわずかにアップダウンして進む。
この先、長らく薮道として認識されてきたが、2025年現在は刈り払いがあって歩きやすくなっている。
小杉山

小杉山は、白岩岳への縦走路との分岐となる。
2025年現在、白岩岳方面は灌木に塞がれた手強い藪となっている。

展望がいいと、この先の和賀岳への稜線が見えるのだが、ゴールへ至るアップダウンにまたしてもため息が落ちる。
だが、薬師岳までのゴリッとした登りに比べれば、この先のアップダウンは見た目ほど手強いものではない。
気持ちのいい稜線歩きを楽しみながら、のんびり行こう。
小鷲倉

国土地理院の地形図に、1354と書かれたピークが小鷲倉。
名前に「小」が付くからには「大」もありそうだと調べたら、目指す和賀岳こそがその別名を「大鷲倉」なのだそう。
和賀岳は他にも名前を持っていて、秋田県からはかつては「大日岳」と呼ばれていたようだ。
たしかに、薬師岳とセットで眺めたなら大日様を名乗るとよりこの山域のありがたみが増す。
小杉山からこの小鷲倉を眺めると、その登りが嗚呼とため息を誘うのだが、ここまで来ればもう和賀岳は手中に収めたと言っていいほど、近くなる。

和賀岳山頂へ

山頂直下は、ここまでの灌木帯から一転、わずかだが草原が広がる。
雪が遅くまで残るゾーンなのだろう。
初夏には、1400mという標高ながらもチングルマが先揃って、ここだけまるで高山のような景観だ。

山頂はなだらかで広い。
小さな祠と、三角点が、砂礫の裸地で出迎える。
夏には、ハクサンフウロやミネウスユキソウ、ニッコウキスゲやトキソウなどなどで賑わう。

山頂から、小鷲倉方面の眺め。

こちら、岩手県からのコースにあるコケ平。
カマボコみたいな稜線だなと、毎度思う。

山頂はくるりとニッコウキスゲの群落を纏う。
薬師岳付近のニッコウキスゲのピークが過ぎてからがこの辺の見頃。
北側には、田沢湖の湖面も見える。
もちろん、秋田駒ケ岳やその手前の羽後朝日岳も。

田沢湖アップ。
このコースの注意ポイント
熱中症対策
コースが長いのと、ニッコウキスゲ見たさに日照時間の長い初夏に、登山者が集中する。
昨今は、東北の山でも夏は気温が高く、またこのコースは稜線に出ると水場や木陰がない。
もちろん、避難小屋もなくましてや営業小屋も売店もない。
つまり、夏場は15キロの道のりを必要な飲料を背負って歩く体力と経験が必須である。
また、悪天時の稜線上では逃げ込めるところも少ないので、天候を見極める知識や経験、そして判断力が必要となる。
飲料水など荷物から少しでも解放されたい場合は、涼しくなる9月下旬から10月ごろが狙い目だが、日の入りも早くなるので、日没前に下山完了できる脚力または、日の出前からの出発となる。
クマ対策について
クマの生息域であるので、早朝や夕方はその対策もしておきたい。
音を立てる対策で、有効なのは釣鐘型の鈴。
ラジオを鳴らして登山する傍迷惑な登山者もいるが、残念ながらラジオはさほど音が届かない。
ラジオを鳴らすのは、拠点を置いてその周辺で山菜採りをするときのものである。
また、カウベルを何個もぶら下げてさながら牧牛のような登山者もいるが、相手は耳の遠い人間ではない。
クマへの対策というよりは、他人にとってただただ騒々しいだけで、本人にとっては邪魔くさいだけだろう。
釣鐘タイプの鈴ひとつ、そして獣用のトウガラシ成分を含む線香、クマスプレー、それでも不安な場合はヘルメット。
このコースで、私はクマを直接見たことはないのだが、獣臭や動物の気配を感じることはよくある。
獣臭の場合はすぐにそれと分かる強烈な悪臭だ。
臭いがしたら、ホイッスルを吹くなり、大声を出すなりすれば割とすみやかに臭いが消えるので、臭いの主のクマが遠ざかったことが分かる。
だが、この獣臭はクマがいれば必ずあるものでもない。
臭はないが、いそうだなと感じたら、鈴を鳴らしたり、手を叩いたり、大声出したりと対策をする。
笹薮でタケノコに夢中になっているとクマは、人への恐怖よりも食欲が勝りがち。
逃げるのが億劫で、唸り声でこちら威嚇することもあるようだ。