南本内岳は、焼石岳のすぐ北に位置する1492mの、どちらかといえば
マイナーな峰だ。焼石岳山頂から30分ほどで立ち寄ることができるので、
この頂を目指して訪れる、というよりはむしろ
焼石岳のついでに立ち寄るという登山者が多いかと思う。
そんな脇役的な山であるが、
岩手県の西和賀に南本内岳の登山コースがあることを知り、
興味を持って4、5年程前に目指したことがある。
あいにく、登山口に至る約15kmの林道が
入って数キロの地点で通行止めとなっていて、がっかりして引き返した。
その後も、西和賀のホームページをチェックするも
大雨などのあとはこの林道がしょっちゅう通行止めである。
今年、たまたま予定していた山行がキャンセルとなったので
南本内岳を検索してみると、林道は通行可能となっており、さらには
数日前が山開きだったようだ。これは林道、登山道ともに
コンディションは最高だろう、ということでいそいそと出かけた次第。
=======コースタイム========
登り=3時間 / 下り=2時間
07:55 登山口
09:08 新倉沢分岐
09:21 ブナ清水(水場)
09:47 お花畑入り口(尾根コースとの分岐)
11:00 南本内岳山頂(休憩)~11:30
12:14 お花畑分岐
13:30 登山口

現在、災害で通行止めとなっている国道107号線から、
錦秋湖ダムにかかる天ガ瀬橋を渡り、
高速道路脇をかすめて、かの林道に入る。
林道はところどころ、路肩崩れ注意のリボンがあるものの
おおむね問題なく、登山口まで繋がっていた。
7時30分過ぎ、駐車スペースに到着。路肩がやや広くなった程度の
駐車スペースと、この上にも車を停められるスペースがある。
先行者の車は一台。すでに出発した様子。身支度していると
もう一台来て、どうやらこの山域をパトロールする地元の案内人の方。

7時55分、蚊取り線香をぶら下げて出発。
登山者名簿の箱の中には、
西和賀の山々のとても分かりやすいガイドマップがある。
しばらくは、なだらかな杉の造林地を、
咲き始めた矢車草の花を左右に見ながら進む。

まもなく沢を渡れば、杉林はブナの森に変わっていき、
徐々に、登山道には傾斜が出てくる。

地元の標識の「一」。ここらから尾根筋の、本格的な登りとなる。
風もなくじっとりと汗がにじんでくる。
先行のグループに追いついてしまい、どうぞと路を譲られた。
譲られたものの、しょっちゅう写真ばかり撮っての山行なので
またすぐ追い越されそうである。

尾根の山腹を巻くようにつけられた登山道に、
年季の入った大きなブナがあり、その割れた幹の途中に
ヤシャビシャクという、希少な植物があると教えられた。
遠くて、よく見えないのが残念。

8時26分、標識「二」。
登山道は痩せた尾根道となり、ささやかながらも風が通って爽やかだ。

痩せ尾根には、五葉松など、松の類いが元気がいい。

細かな松の葉が堆積する登山道は、とても歩きやすい。

歩きやすいのもそのはずで、倒木などはほぼ処理されているのだ。
切り口などは、新しいものも多くおそらく
山開きに合わせて、丁寧に登山道が整備されたのだろう。
写真の丸いプレートには、
「新倉沢まであと5分」と手書きで書かれている。

本日、ギンリョウソウが多かった。
地味であるが、気がつけばギンリョウソウ街道となっていた。

9時5分、新倉沢。石伝いに難なく渡れた。

沢の対岸には本日初のハクサンチドリがお出迎え。

新倉沢からやや急な登山道を20mばかり登ると
尾根コースとの分岐がある。
今日は、行きをこの尾根コースを使って8の字ルートを
目論んでいたのだが、

国土地理院の地形図には記載のある登山道の方向を見ると、
意味深に木の枝が置かれている。
跨いでその先を覗いてみると、草がみっちり。
木の枝はこの先通行不可のサイン。よく見ればその脇にある標柱に、
登山コースを示すプレートが剥がされていた。
どうやら廃道となって久しいようだ。

大人しく、お花畑コースを辿る。
こちらは、本当にすばらしく手入れされて
いる。
いる。

湿地の木道脇に、今年初モノのサワモタシ。

9時21分、ブナ清水到着。
プレートには「水質は保証しない」旨の記載があったが、
キンとした冷え具合にたまらず、一杯。
しぼり取られた汗の分、細胞に染み渡るおいしさだ。

9時25分、水場からすぐの場所に苔むした岩を洗って流れる沢。
CMにでも出てきそうに涼しく気持ちのいい場所。
休憩するにはちょうどいい。

登山道脇にはモミジカラマツ、カラマツソウが咲き始めていて見頃。
ほかにもハリブキ、コヨウラクツツジなども。

樹木の背が少し低くなり、足元にイワカガミなども現れてくる。
登山道は、ごらんの通り、要所要所で階段が作られている。

そして、これ!えぐれた登山道の横の斜面のステップに、
足一個分の滑り止めが施されていた。
おかげで、不安無く通過できる。
西和賀の心遣いの細やかさには感動してしまう。

9時47分、尾根コースとお花畑コースの分岐。
本日は、お花畑コースから登り、尾根コースを下ってくることにする。

イワイチョウが咲く湿原へ。

伸びやかな湿原。脚がなかなか進まない。

ミツガシワが見頃。

シナノキンバイも。

コバイケイソウと、シナノキンバイ、ミツガシワ、
ハクサンチドリなどの群落をのんびりと歩く。

この湿原を越えて少し行けば、またお花畑があるらしい。
駐車場で会った地元のパトロールの方から教えてもらう。

見事な花畑に誘われながら、緩やかに高度を上げていく。
振り返ると、さきほどの湿原と池塘。

間もなく、教えられた湿原に到着。さらに広く、雪渓もある。
小川も流れ、焼石岳の焼石沼付近に似た雰囲気だ。
ひんやりとした空気に汗が引く。

お花畑を過ぎると、いよいよ最後の登りだ。
高度が上がると、西に三界山が見えてくる。奥には大森山。

ハクサンシャクナゲが、ちょうど見頃だった。
私はいつもボロボロになった頃合いしか見たことがなかったので、
この咲いたばかりの新品を見たのは、今回が初。

尾根に上がると、ウスユキソウの類いも登場。
う~ん、ミネウスユキソウかな。

カエルも登場。

10時57分、焼石岳からのコースとの分岐。
山頂はすぐそこ。

11時、山頂。
ちょうど先月の今頃もここにいた。
あちらは焼石岳。入れ替わり立ち替わりのように
数人のグループが山頂に立つのが見える。賑わっていそうだ。

先月は山頂付近はチングルマが見頃だったが、
本日は数輪残して、産毛状態に。

他のグループもまだまだ到着しそうにないので、
山頂を独占してランチタイム。途中で採ってきたタケノコと
乾燥わかめを入れて、豪華カップラーメン。

11時30分。グループの声も近づいてきたので、そろそろ店じまい。
山頂を明け渡して下山に取りかかる。下山には尾根コースを使う。
こちらの道も刈り払われたばかりのようで、とても歩きやすかった。

コメツツジ。1センチにも満たないような小さいツツジだ。
5年前に、羽後朝日で見て以来の再会。

パトロールの方に教えてもらったハクサンシャクナゲの大きな木。
見頃。痛んでいないハクサンシャクナゲも初めてなら、
こんな見上げるようなハクサンシャクナゲも初めてだ。

アカミノイヌツゲ。赤い実が着くイヌツゲ。雌花。
大きさは3~4ミリぐらいのちっさな花。
登山道脇にたくさんあって、イヌツゲロードとなっていたが
果たしてこの花盛りに気づく人がどれほどいるか。

尾根コースも、素晴らしく整備が行き届いて歩きやすい。

振り返ると、南本内岳山頂に、今朝追い越したグループが立つのが見えた。

伸びやかな尾根歩きが終わると、
眼下の湿原目指して、ぐんぐん標高を下げていく。

当初、8の字ルートを取ろうとして廃道となっていたコースは
あの目の前の山の山腹を巻いて鞍部に上がり、
そしてこちらのこのコースと合流する。
途中、その合流ポイントらしき標柱があったが、道らしき形跡は
薮に覆われて見つけられなかった。

12時12分、池塘のある湿原に飛び出る。
お花畑分岐はここからすぐだ。

今朝は気づかなかったが、お花畑分岐付近にオオバタケシマラン。
葉っぱの下に隠れるようにして花が着くので
なかなかその存在に気がつかない。

あとは今朝と同じ道を辿って登山口へ。
ヤグルマソウのゴージャスな花の街道を抜け、
13時30分に登山口到着。
出発時には3台だった車はさらに増えていた。
マイナーな山だと思っていたが、知る人ぞ知る穴場的な山として
人気があるようだ。
大雨のあとなどは、林道は崩壊しやすいのでご注意を。
天気が大きく崩れそうなときや、大雨の後は林道の状態を確認してから
入山するのが安心。

下山後温泉は、温泉地なので選び放題だ。
穴ゆっこ、砂ゆっこなどユニークなものもあるが、
本日はほっとゆだ駅の温泉、300円。
温泉のあとは、向いにある湯夢プラザの食堂で蕎麦。
写真は十割そばの大ざる。二人前ぐらいある。
西和賀は、他にも真昼岳や高下岳から和賀岳、
女神山などの登山コースを持つ。
ホームページに林道情報がこまめに更新されてアップされているので
チェックしてから出かけるのがおすすめ。
下山後はぜひ、温泉とおいしい蕎麦、
そして湯田牛乳で作るソフトクリームを!そして時間があれば
貯砂ダムで涼むのも良い思い出になるでしょう。
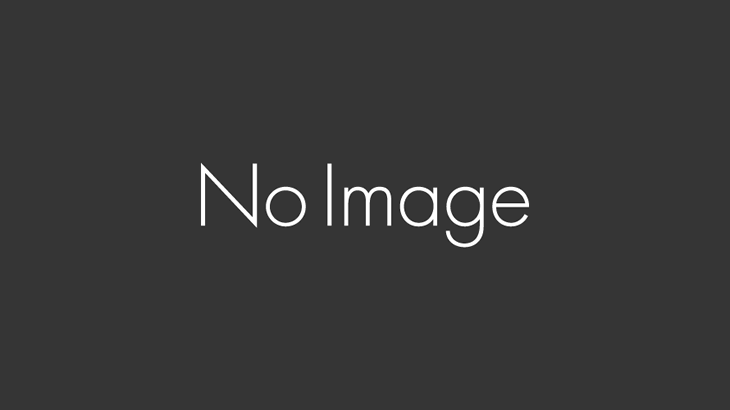
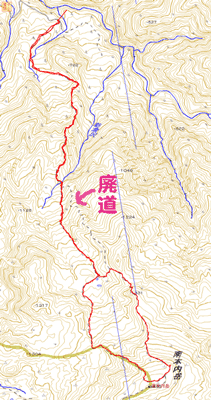

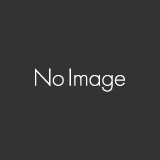



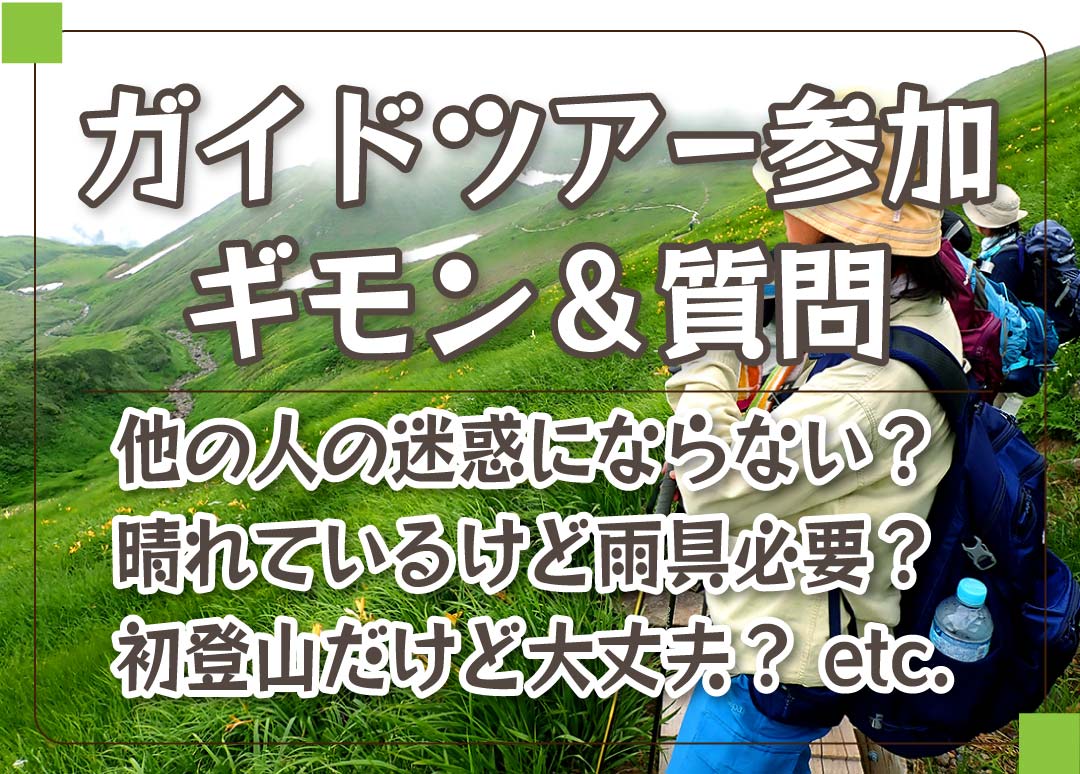

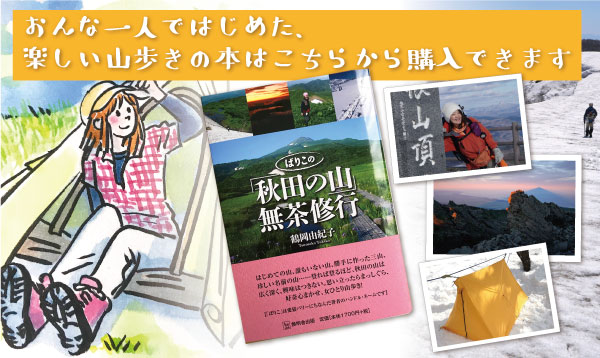
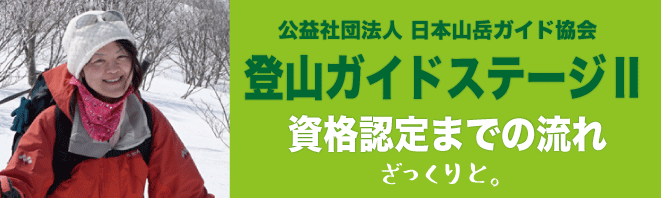



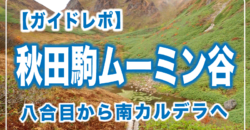



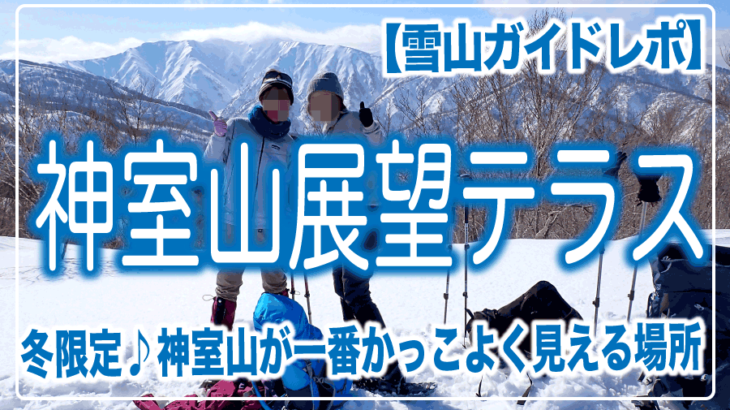
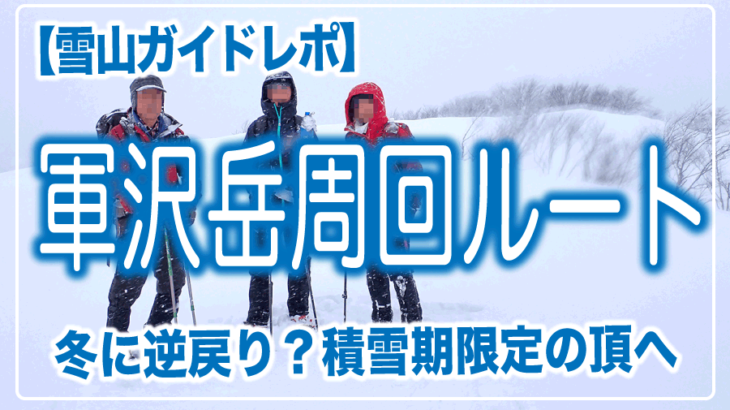
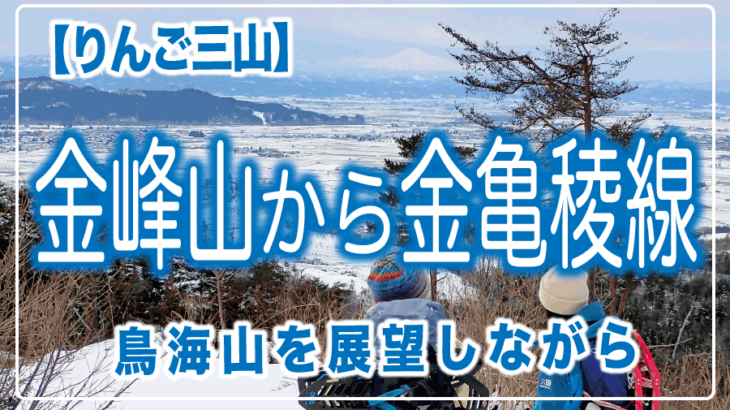

コメントを書く