
低体温症はなぜコワい?
低体温症というのは、体温が低くなることで体が正常に動けなくなり、放っておくと死にも至ることがあるコワイ症状のことです。
ご存じのとおりヒトは恒温動物。
体温がほぼ一定に保たれることで正常に動き生活することができます。
体温を一定に保つために、暑いときは発汗などで体から熱を逃す反応があったり、寒いときは震えなどで体を温めようとします。
ところがこうした機能で追いつかないほど、体温の変動があったとき、暑いときなら熱中症に、そして寒いときはどんどん体温が下がってしまう低体温症のリスクが高まります。
こうなると体を動かす機能だけでなく、脳機能にまで異常が生じてしまうのが怖いポイントです。
脳が働かなくなってしまうと、寒いのにそれを防ぐ考えや判断ができなくなって、ついには錯乱状態にまでなってしまうのです。
山でそのような状況になってしまうと、救助が難しくなってしまいます。
恐ろしい低体温症ですが、正しい知識と装備があれば防ぐことができるもの。
ここでは登山者なら知っておきたい、低体温症について説明します。
低体温症を予防するために知っておきたいこと
どうして体温が下がるの?
体温はどんなときに下がるのでしょう?
もちろん気温が低いときですね。
低い気温は体温を奪います。
しかし体温を奪うものは気温だけではありません。
つまり気温による寒さだけを防いでも、低体温症の予防にはならない場合があるということです。
ここに低体温症予防のための、正しい知識のポイントがあるのです。
体温を奪う現象は4つあります。
・対流
・伝導
・蒸発
・放射
ちょっと聞き慣れない言葉ですね。
ということで上のムズかしい言葉を、登山中のよくあるシチュエーションで説明しますね。
【対流】
風によって体温が奪われる現象がコレ。
風速1mにつき体感温度は1℃下がります。
たとえ気温が15℃でも、風速15mの風が吹けば体感温度は0℃ということになります。
【伝導】
濡れた服を着ているとひんやり感じます。
また冬にピッケルの金属部分に触れていると、指先が冷えて凍傷になることもあります。
これは冷たいものに触れることで、自分の体温が奪われるため。これが伝導です。
【蒸発】
人が汗をかく理由は、気化熱によって体温を下げるため、という話を聞いたことがあるかと思います。
水分は蒸発するときに熱を奪います。
体が濡れていると、肌の水分が蒸発しますのでこのときに、どんどん熱が奪われてしまいます。
これが蒸発です。
【放射】
あたりまえですが、暑いとき上着をぬぐと涼しくなります。
寒い日に一枚脱ぐと、涼しいどころか寒くてなりません。
それは、上着などで閉じ込められていた熱が逃げてしまうためです。
これが放射。
もっとわかりやすい状況で例えましょう。
たとえば、風のない樹林帯を登っていると暑くて汗が噴き出ます。
体が汗を蒸発させるときの気化熱で、体温を下げようという反応です。
暑いなと感じた人間は帽子を取ったり衣類を脱いだりします。
ちょっと涼しく感じますね。
衣類をぬぐことで熱が放射されたわけです。
やがて稜線に出ると風が吹き付けました。
標高が上がって気温も下がりました。
寒く感じて一枚上着を着ます。
これが対流、つまり風や気温による体感温度の低下です。
立ち止まったついでに小休止したのですが、今度は上着を着たのに全然温まらない。
むしろ寒いくらい。
それもそのはずです。
衣類が汗で濡れていたのです。
これが伝導ですね。
濡れた衣類という冷えたものに触れて体温が奪われるのです。
同時に体も濡れているので、蒸発も起こっているかもしれません。
こうしてみますと、登山では体温を奪う要因が複合的にあることがわかりますね。
こうした外からの要因ともうひとつ、熱を発生させる体の内面の要因も忘れてはなりません。
熱を発生させるとき、人の体はエネルギーを使います。
このエネルギーが十分でないと体温が上がらないこともあります。
震えがきたらヤバい!低体温症の症状を知ろう。
寒かったら何か着ればいいじゃないか。
そう思います。
もっともです。
ところが低体温症の恐ろしいところは、そんな簡単な判断と行動ができなくなる点にあります。
・面倒だから
・ほかのメンバーの足を止めると迷惑になるから
などの理由で登山中に寒さを我慢したり、濡れた衣類を放っておくと体温はどんどん下がっていきます。
やがて34℃まで深部温度が下がってしまうと、脳が正常に働くことができなくなります。
結果、自分では寒さから体を守るための思考や行動ができなくなるのです。
このことから分かるのは、山で低体温症に対処できるのは、最初の震えがはじまった段階まで。
震えというのは、筋肉が振動することで熱を生み出そうとする体の防衛反応です。
震えにはたくさんのエネルギーが消費されます。
その震えがなくなるということは、体にはもう熱を生産するためのエネルギーがなくなってしまったということ。
こうなってしまうともう山では体温を上げることができません。
震えがはじまったときには、すでに低体温症の入口にいるようなものなのです。
次の表に深部温度が下がったときの症状をまとめております。
できれば寒さを感じた段階で低体温症対策が必要だと心得ましょう。
| 深部温度 | 症状 |
| 36℃ | 寒さを感じる |
| 35℃ | 震えがくる。動作や歩行がのろくなる。 |
| 34℃ | 震えが強くなる。うまく喋れなくなる。無関心になる。返事をしない。転倒しやすくうまく動けない。 |
| 〜32℃ | 転倒する。錯乱状態になる。会話ができない。動けない。 |
| 〜30℃ | 震えが止まる。立ち上がれない。錯乱状態になる。意識を失う。 |
| 〜28~26℃ | 半昏睡〜昏睡状態に。脈が弱い。瞳孔が開く。
心停止に至る。 |
誰でもできる!低体温症にならないための対策
低体温症から自分を守るためには、寒いと感じた時にすぐに対処し、体を極力濡らさないこと。
雨の山で濡れる理由は、雨による直接的な濡れのほか、雨具を着たことによる蒸れによる濡れも大きな原因です。
レインウエア含め登山ウエアには、こうした蒸れによる濡れに対処することで登山者を低体温症から守る機能があります。
・速乾性
・疎水性の高い素材
・雨は通さず蒸れは逃す素材
・濡れていても保温性の高い素材
などさまざまな機能を備えたウエアがあります。
その高機能に比例して高価なのが悩ましいところですが、体を守るシェルターと考えれば納得かもしれません。
低体温症から体を守るには、こうした登山用のウエアを上手に活用することが第一です。
上手に活用というのはどういうことでしょう。
以下にくわしく説明しますね。
汗をかかないようにする
速乾性や吸湿性の高いウエアを着ていても、行動中はどんどん汗をかいてしまうもの。
こうなると、汗で濡れることによる低体温症だけでなく、夏には脱水症や熱中症の原因にもなります。
暑い日も寒い日も、汗をなるべくかかないように行動することが、低体温症含め遭難予防の一歩です。
コツは登り始めの30分は、とにかくゆっくりと汗をかかないように登ること。
最初に大量に汗をかいてしまうと、水分とともに体を動かすために必要なミネラルも早々に失ってしまうことになり、これが熱中症やバテにつながります。
どうしても汗が出てしまいますが、少しでも抑えることを意識しましょう。
その簡単なコツは、出発のときは肌寒いくらいのウエアで。
夏はすでに暑いのでなかなかそうはいきませんが、たとえば
・帽子を脱いだり、
・手袋を外したり
・腕まくりをしたり
・首に濡らして絞ったタオルを巻く
などで工夫しましょう。
ウエアの素材にこだわる
ご存じとは思いますが、登山にコットン素材はNGです。
理由は汗を吸いやすく乾きにくいため。
生地が乾きにくいと冷えにつながります。
山のウエアの素材は次の二つ。
【天然素材】ウールなど
・・・・どっちがいいの?悩みどころですね。
特徴をまとめました。
【天然素材:ウール】
・濡れても保温性が高い
・汗臭くならない
・割高
・虫に食われやすい
【化学繊維:ポリエステル】
メリット
・速乾性が高い
・軽い
・コスパがよい
デメリット
・汗臭くなる
ウールはちくちくしたイメージがありますが、スーパーメリノウールという素材なら、肌ざわりも柔らかで着心地もとても良い生地です。
濡れていても保温性が高いので、立ち止まることの多い登山の場合、特に寒いシーズンにはおすすめです。
化学繊維のほうは登山用ウエアのポリエステル100%を選びましょう。
一般的なスポーツウエアでも、ポリエステル100%素材はありますが、速乾性や吸水性、着心地の快適性は登山用ウエアのほうが上です。
快適な方を選ぶ、といえば何だか贅沢をしている気分になりますが、登山という過酷な場において快適ということはそれだけ体への負担が少ないことになります。
体への負担がなければ不要な消耗が避けられます。
一日中歩くことがほとんどの登山では、体力をなるべく温存するため快適であることも必要な要素です。
ウエアのレイヤリングにこだわる
寒いからといって分厚いウエア1枚で解決!
なんてことはしていませんか?
山のウエアは体温調節のためのアイテム。
体温調節のためには次に挙げる3レイヤーが基本です。
【アンダーレイヤー】肌着
体温調整のためには、特にアンダーとミドルの枚数を調整します。
ミドルを2枚にしたりアンダーを2枚にします。
衣類の保温は衣類と衣類の間に空気層をつくることがコツ。
ダウンジャケットが暖かいのも、羽毛がたくさんの空気層を作っているからですよね。
だったら厚いウエアでも、生地に空気層ができるからいいのでは?
いいえ。
山では行動中に暑くなることがほとんどです。
そうしたときに複数枚を着ていれば、一枚脱ぐことで簡単に体温調整ができます。
もしミドルで枚数を増やしても、まだ寒そうっていうときはサーマルウエアを装備します。
サーマルウエアは
・フリース
・ダウンジャケット
などがあります。
暑がりな人や夏などは、ベストタイプのサーマルウエアがおすすめです。
ウールの腹巻きも便利です。
ただしダウンジャケットは、汗などで濡れると保温性がなくなります。
行動中に着用するには向きませんのでご注意を。
ドライレイヤーを活用する

ドライレイヤーはもはや、登山ウエアリングの定番になっているかもしれませんね。
メッシュ状の薄い生地のもので、アンダーウエアのさらに下に着用します。
疎水性が高いので、体の汗を素早く吸収してアンダーウエアに送ります。
これによって、肌は比較的サラリと保たれます。
わたしも愛用しておりますが、汗をかき続けるような環境ではアンダーからミッドの乾燥が追いつかないのでそんなにカラッと快適とはいきません。
とはいえたとえばビバークで冷えから体を守るとき、そんな極限状態ではこの薄い一枚のレイヤリングが生死を決めることも確かです。
的確にエネルギーを補給する
体を温めるためにはウエアリングも大事ですが、体内からちゃんと熱を生み出すことも大事です。
寒いなと感じたらウエアを着込むと同時に、一口でもエネルギーになるものを補給しましょう。
行動中もこまめに食べることを意識します。
2009年7月に北海道のトムラウシ山で起こった遭難では、低体温症による死者が大勢いました。
無事救助された人の話を聞きますと、的確に衣類調整をしていたことと、ポケットにアメなどを入れて常に食べられるようにしていたと語っております。
体のなかに熱源を絶やさないこと、これも低体温症予防には大事です。
トムラウシ山の遭難事故報告書は日本山岳ガイド協会HPで詳しく読むことができます。↓↓
https://www.jfmga.com/tomuraushi.html
寒くならないための対策をする
いったん冷え切ってしまうと、なかなか体が温まらない経験はないでしょうか。
熱源として、使い捨てカイロを夏でも持っておくことをおすすめします。
カイロがないときのために、夏でもポットにお湯をいれておきましょう。
体が冷えてしまったときにこのお湯を、折りたたみボトルなどに入れると湯たんぽになります。
お湯を入れるときに火傷をしないように、折りたたみ漏斗があると安心です。
百均のダイソーでも入手できます。
湯たんぽは火傷に注意してください。
山の中での火傷は冷やすための水も限られますので、下界以上に注意が必要です。
下山する
体温をあげる対策をしても、まだ寒く震えも始まったとしたら可能ならば下山するのも手。
標高が下がれば気温は上がりますし、樹林帯に入れば風からも体を守ることができます。
まとめ
低体温症は防ぐことのできる遭難ですが、そのタイミングを逃してしまうと取り返しのつかない状態になってしまいます。
かくゆう私も、低体温症の手前に陥った経験があります。
古いレインウエアで撥水性がなく、あっというまに衣類が濡れてしまい、とにかく寒くてたまりませんでした。
ついには喋るにも歯の根が合わないくらいに震えがきて、これはまずいなと思いながら下山しました。
寒いながらも、お腹いっぱいにきりたんぽ鍋を食べたこともあってか、だんだん体温が上がりましたが、
もしあのとき何かのアクシデントが起こって、停滞しなければならなかったら、そう考えるとゾッとします。
低体温症対策で大事なのは次の3つ。
・寒い日は意識して食べる
・寒さ対策を躊躇わない(他のメンバーに遠慮しないこと)
山では低体温症に陥る要因がとても多くあります。
しかしちょっとした心掛けと正しい知識があれば防ぐことができるのです。
こちら低体温症手前まで行った雨天の乳頭山ブログです。





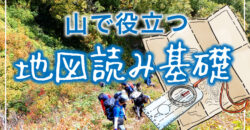



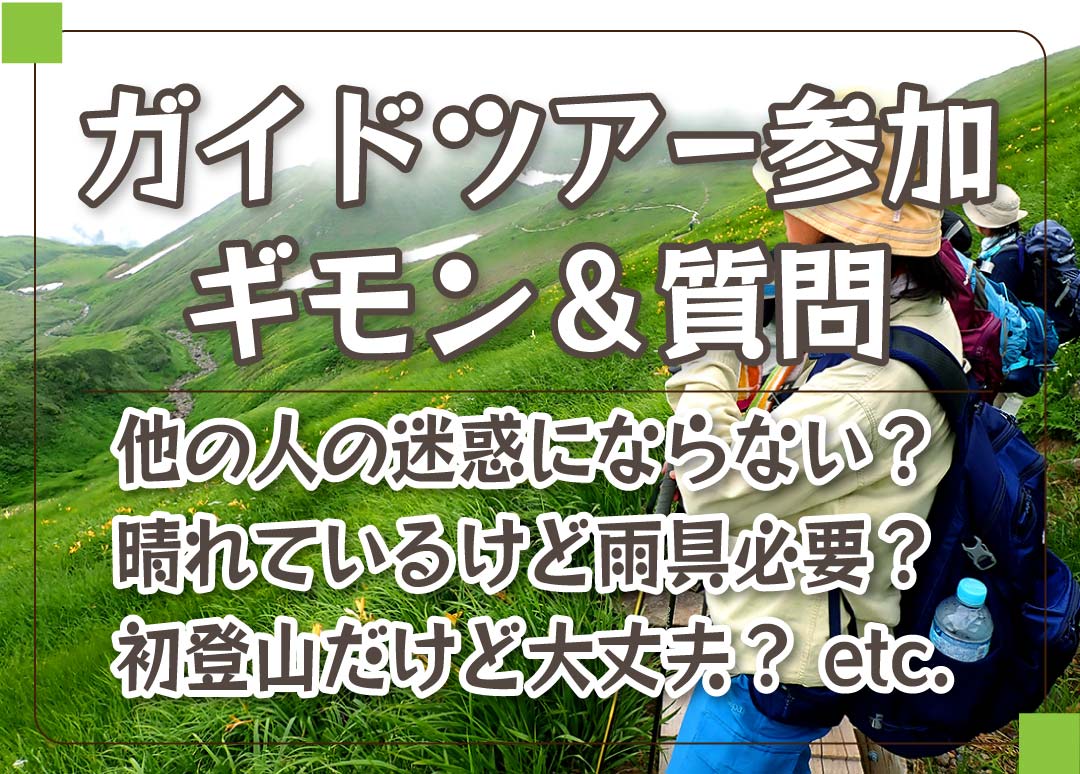

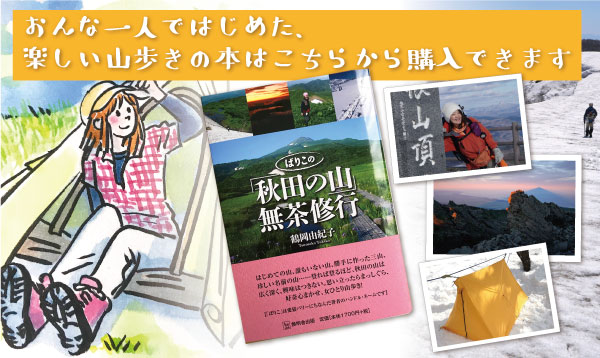
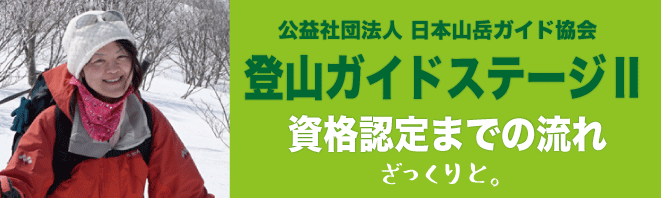



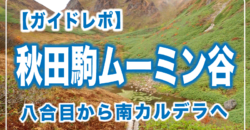

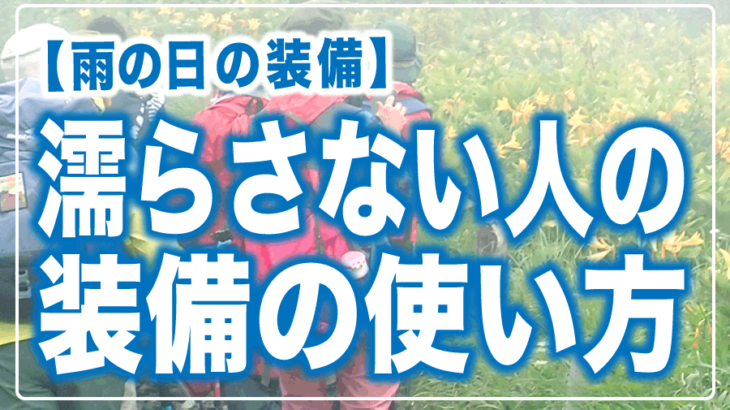


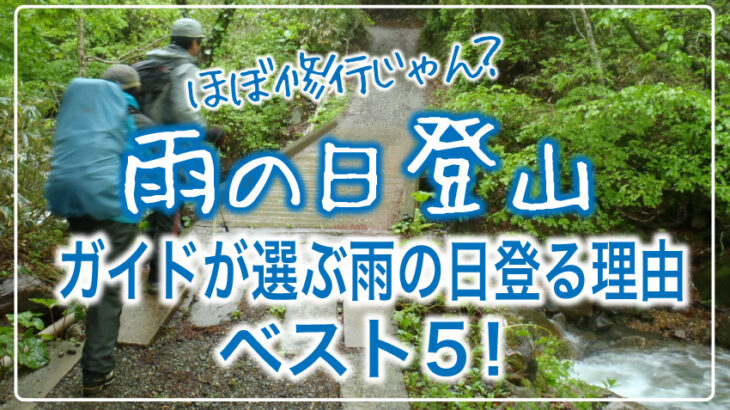

コメントを書く