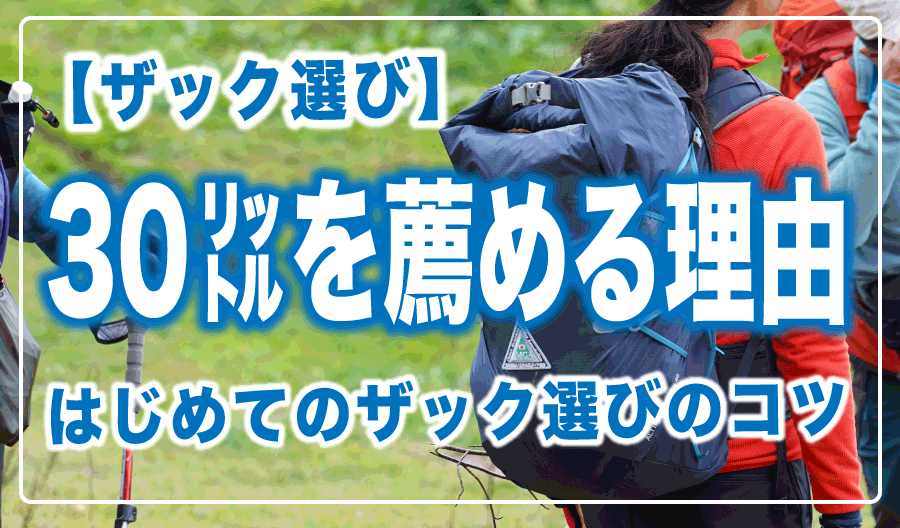
さあこれから登山をはじめるぞ!となったとき、まず揃えるのは登山三種の神器とも呼ばれる登山靴、ウエア、そしてザック。
しかしいざショップに行ってみれば、サイズもブランドもたくさんでどれがいいのかわからない!
ザック選びは登山を始めるにあたっての第一関門かも。
そこで、これから登山を始めるという人に、登山ガイドがおすすめしたいのが30〜35リットルサイズのザック。
けれど、登山初心者にとってこのサイズは、かなり本格的に感じられて、気後れしてしまうという人も少なくない。
それでもこのサイズを強くおすすめする理由をくわしく説明したい。
30L台サイズをすすめる理由
荷物事情の実際①:初夏から夏山

おそらく初心者が登山をはじめる時期は、初夏から夏の無雪期という人が多いだろう。
メインの荷物は雨具、飲料、食糧、防寒着。こんなところ。
防寒着もさほど厚い衣類は不要で、予備のグローブなどももちろん不要だ。
この期間だけならば、25L程度が最も手頃なサイズである。
荷物事情の実際②:秋から晩秋

やがて冷えこむ季節になってくる。
山の夏は短い。8月下旬ごろから秋の花がみられるようになり、9月は一雨ごとに冷え込んでいく。
日足も早くなり朝夕は冷え込む日も増えてくる。
気象にあわせて防寒着やグローブ、寒さに備えての帽子など嵩張る荷物が増える。
温かい飲み物も持ちたくなる。
あるいは冷え込む早朝の出発時に着込んでいたフリースを、暑くなってきたので仕舞いたくなる。
しかし、こうなると20L台では、こうした荷物が収まりきらなくなる。
なんとか押し込むことができても、今度はザックが閉まらない。
というのも小型ザックでは、本体の開閉がファスナーという場合がほとんど。
ファスナーだと、あまりに荷物が多すぎるとなかなか閉まらなくなってしまう。
そこで仕方なくザックにくくりつけたり、腰に巻いたりと対策がとられるのだがこうなると、
・木の枝などに荷物がひっかかってバランスを崩しやすい
・荷物を落としやすい
という恐れもある。
これが30L台サイズであれば、当然だが余裕で荷物をパッキングできる。
またザックが中型サイズになると、本体の開閉方法はファスナーではなく、ロールトップや巾着タイプがほとんど。
この開閉方式ならばたとえ荷物が多くなってしまっても、何とか工夫して締めることもできる。
荷物事情の実際②:小屋泊りがしたくなる

登山にハマるにつれ、小屋泊登山にも興味が出てくる。
30L台ならば、営業小屋一泊程度の荷物なら問題なくパッキングすることができる。
いっそのこと、もっと大きいサイズのほうが良いのでは?
40Lや50Lのほうがさらに汎用性が高いのでは?
たしかに大は小を兼ねるとの言葉通り・・・ではあるのだがザックも大きくなればその分、重くなる。
山歩きに慣れないうちや、体力の低い人にとっては余分な重さは体力を奪うだけである。
30L台ザックに入る荷物もっと詳しく

こちらの画像は私の、無雪期におけるガイド業務中の30Lザックの中身。
ガイドであれば、30L台サイズは業務の荷物が入るジャストサイズだ。
しかし一般的な登山者であれば、ツエルトはこの半分サイズ、ロープなども持たないだろうし、ファストエイド品も自身のためのものだけになるためもっと少なく済む。
ざっと下記の内容が標準的な日帰り登山の持ち物となる。
②行動食・昼食・非常食
③飲料
④ファストエイド品
⑤ツエルト
⑥状況によって持つべき装備
□アイゼンやチェンスパ
□脱いだ衣類
□予備のグローブ
小屋泊まりなら以上の装備に、次のものをプラスする。
□着替え類
□翌日の食糧等
□歯ブラシやメイク落としスキンケア品
□モバイルバッテリー(充電できる小屋もあるが)
後悔しないためにチェックするポイント
それでは中型サイズとも呼ばれる30L台サイズのザック、どう選べばいいだろうか。
ここからは、納得のいくザックを選ぶために最低限チェックしておきたいポイントと、登山者各自のこだわりたいポイントをまとめてみた。
購入前にぜひご参考に。
ポイント①体に合うザック選びのコツ
背負って快適なザックというのは、疲れにくいザックである。
登山において疲労は、集中力の低下や運動機能の低下の要因となり遭難のリスクも高まるもの。
重い荷物を背負っても、いかに疲れにくくするかの第一歩は、体に合ったザックを選ぶこと。
とはいえ、店頭で背負ってみていいのか悪いのかなんて、分かるものではない。
それでは何を基準にしたらいいのだろう。
それは背面長という、背中の長さ。これが体に合うザックの大きな決め手となる。
背面長(はいめんちょう)

背面長とはザックの背中部分の長さのこと。
このサイズが、自分の背面長に近いこと。
それが体に合うザック選びの基準になる。
自分の背面長の測り方
- 首を前に深く傾けたとき、首の後ろを指でさわってみて最も飛び出ている骨(第7頸椎)を探す。
- 腰に手を当て、骨盤の一番高い部分(腸骨稜)を探し、その高さにある背骨を探す。
- 1と2で探した骨2点間の長さが背面長(目安:40〜50cm程度)。
メジャーなどを使って計測してもいいし、なければ紐などを使って測っても良い。
背面長とサイズ表記
中型〜大型ザックでは背面長を調整できるモデルもある。
| 背面長 | ザックのサイズ(日本サイズ) |
| 〜40cm | Sサイズ/女性サイズ |
| 40〜45cm | Mサイズ |
| 45cm〜 | Lサイズ |
女性の体型に合わせたモデルも
男性と女性では、体格にだいぶ差があるもの。
これまでザックは男性の体格を想定した商品がほとんどだったが、昨今は女性の体型に合わせた設計のモデルが増えている。
体に合わない大きめのザックを背負うよりも、よりフィット感があり疲れにくい。
女性用ザックの特徴は以下の通り。
□背面長が短め
□ショルダーハーネスの幅が狭い
□胸を圧迫しない位置のハーネス形状
□ウエストベルトの角度が調整されている
女性用とはいえ、女性だけではなく身長が165センチ未満であったり、胴が短い、肩幅が狭いなど小柄な人でも体に合えば選ぶのも良い。
ポイント②荷物へのアプローチ
ザックの背面長がわかったら、次にチェックするのはザック本体の開閉方式。
30L容量ザックだと、次にあげる3つの開閉方式がほとんどだ。
どんな特徴があるのか理解して、自分の山行スタイルに合うものを選ぶことになる。
本体トップの開閉方式
登山初心者が30Lサイズのザックを選ぶ際、おすすめの開閉方式はトップローディング。
特に目的や好みがまだ確立していない、登山初心者が最初にザックを選ぶなら、スタンダードなこの開閉方式のモデルのほうが汎用性があり妥当だと考える。
開閉方式についての詳細は下の一覧表を。
| トップローディング (巾着+天蓋)  |
パネルローディング (ファスナータイプ)  |
ロールトップ
|
| 開閉方式種類 | 特 徴 | メリット/デメリット |
| トップローディング
|
ザックの上部から荷物を出し入れする、最もスタンダードな開閉方式。 |
□メリット
・多少の容量オーバーOK ・雨でも水が入りにくい
□デメリット ・一気室の場合ザックの底の荷物が取り出しにくい。 |
| パネルローディング
|
ファスナーでザックの前面がガバッと開くので、中が見やすく荷物の出し入れがしやすい。 |
□メリット
・中が見やすい ・パッキングがラク
□デメリット ・ファスナー部分から浸水しやすい
・容量オーバーだと閉まらない |
| ロールトップ
|
開口部をくるくると巻いて閉じる方式。もともとはカヌーや沢登りなど、
高い防水性が求められるシーンで発展。
|
□メリット
・構造がシンプルで軽量 ・容量の増減に柔軟対応 □デメリット
・下の荷物を取り出しにくい
・フレーム構造がないなど、背負い心地が良くないモデルもある。 |
サイドや背面などからのアプローチ
側面や底部などに本体にアプローチできるファスナーがあると、わざわざザックのトップを開閉しなくてもさっと荷物の取り出しができて割と便利。
ファスナーが損傷したら閉まらなくなって困るのでは?
そんなリスクもゼロではないが、これまでわたしが使用してきた限りでは壊れた経験はない。
山道具はかなり丈夫に作られているので、よほど壊す気まんまんでもない限りはあまり心配しなくてもいいかなと個人的には思う。
選ぶポイント③ポケットなど収納
すぐに取り出したいものや、頻繁に出し入れするものを収納するのに便利。
サコッシュやウエストバックを使う人も多いが、これらは場所によっては邪魔だったり危険だったりも。
たとえば、岩場通過のとき、ウエストにバックがあると足元が見えにくかったり、岩や木の枝にひっかかってバランスを崩す恐れも。
危険箇所通過時には、このような荷物はザックにしまうなどの対策が必要となってくる。
一方、ザックに小物収納があれば、比較的、動作への干渉も少なくて済む。
次にどのようなポケットなど収納があるのか説明しよう。
①天蓋

ザックをおろしてすぐに出し入れしたい小物や行動食などの収納に。
ココヘリ端末も天蓋に入れておくのがイチ番安心。
わたしは、天蓋の小さなポケットににココヘリと、ちょっとしたファストエイド品。
大きなポケットには、菓子パンやゼリー飲料など行動食を入れておくことが多い。
②ショルダーベルトのポケット

ザックを背負ったまま出し入れできるので、行動中に頻繁に使うものの収納に便利。
③ウエストベルトのポケット
| 例)ミレー:サースフェー
|
サースフェー:拡張できるモデル
|
ザックを背負ったまま出し入れできるので、行動中に速やかに取り出したいものの収納に便利。
たとえば、行動食や地形図、虫除けスプレーや日焼け止めなど。
④ザック側面

マットやトレッキングポールなどやや大ぶりなものも収納できるが、原則としてはザックの中に入れるのが安全だ。
ペットボトルを出し入れしやすい設計のものもあるが、体の柔軟性が低いと一人で出し入れするのは難しい。
また、サイドポケットに入れたペットボトルは、ときどき落とす人も少なくないように思う。
山で飲料を失うのはかなり痛手。
そしてゴミにもなってしまう。
わたしは、側面ポケットはあまり使わない。
⑤ザック背面
スコップや軽アイゼン、スノーシューなどの収納に便利。
選ぶポイント④各メーカーのこだわり設計
①軽さ
少しでも荷物を軽くしたい。
そう考える登山者はかなり多い。もちろん私も。
ただし、軽さ第一で選ぶのは考えもの。
軽さというのは、結局ほかの機能とのトレードオフで成り立つもの。
初心者のうちは、まずは普通のザックを使ってみて自分にとってどの機能なら妥協できるかどうか、把握できるようになってから軽量ザックを選ぶ、という流れのほうがいいと個人的には思う。
たとえば、軽量化のために小物収納ポケットがゼロのザックがある。
しかし使ってみると、結局不便に感じて後付けでポーチなどをくっつけている。
そうなると本体にもともと組み込まれてある収納にくらべ、重くなってしまう。
 |
 |
また、背中に当たる部分のフレーム構造をなくしたモデルが多い。
このフレーム構造を排除すれば確かに軽くはなるのだが、このシステムによって荷物が安定したり、疲労が軽減されたりする機能があるのも確か。
フレームがないと、パッキング次第では背中に荷物が変に当たって窮屈だったりもする。
軽量ザックを選ぶ理由が「疲れたくないから」という場合、疲れにくい設計を犠牲にしてよいかどうか今一度考えてみよう。
などなど、軽量ザックを選ぶときは、何を目的に「軽さ」が必要なのかしっかり自問できるほど経験を積んでからでなければ、かえって疲労感が出るということもあり得るのだ。
③疲れにくいフレーム構造
実は、快適な登山のカギを握るのがフレーム構造。
重い荷物を持って山道を何時間も歩く登山では、いかに体に負担をかけないかについても選ぶポイント。
そもそも「フレーム構造」ってなに?
登山用ザックの中には、荷物の重さを分散するためのフレームが内蔵されているものがある。
これにより荷重を腰や肩、背中全体に効率的に分散することができる。
このフレームがあるおかげで、ザックが体により快適にフィットして、長時間背負っても疲れにくくなる。
フレームによる機能は以下の通り
・荷重分散で疲れにくい
腰と肩にバランス良く荷物の重さを分散するため、長時間の歩行でも疲れにくくなる。
特に縦走や小屋泊まりなどで荷物が重い長時間の行程ほどメリットを感じられる。
・姿勢をキープしやすい。
背中に沿ったカーブが、正しい姿勢をサポート。腰や背中への負担が軽減される。
・安定性があり安全登山に。
体によりフィットするため、ザックの揺れによる疲労が軽減される。
また岩場などの難所で、体が振られることが抑えられバランスを保ちやすくなる。
④通気性

ザック本体と背中の間に空間を作ることで、通気性のあるモデルもある。
夏などはとても快適。
ただし、冬、吹雪の中ではこの空間に雪が入り込むのでそれがイヤという人もいる。
よほどの吹雪の中での登山を想定しなければ、快適なので良いかと思う。
⑤レインカバー付

ほとんどのザックは、雨天ではレインカバーが必要になる。
レインカバーはザックとサイズが合わないと、ザックが濡れたり風で飛ばされやすくなってしまう。
かならず、サイズにあったレインカバーを用意する。
メーカーによっては、ザックにレインカバーが内蔵されているものがある。
もちろんジャストサイズなのでザックとの相性も良い。
しかしレインカバーをしていても、ショルダーベルトなどからザックが濡れてしまう場合が多い。
このため、雨が予想される日はザックの中に防水性の高いスタッフバッグや、ゴミ袋など大きな袋を入れておくと安心。
ガイドが実際に使ってみた中型ザック紹介
おすすめのザックはこれ!
と断言するほどには各種メーカーのザックを試したわけではないので、あくまで私の使っているザックということでご紹介します。
ご参考になれば幸いです。
ミレー:サースフェー30L+5L

じつは、はじめて自分の体格に合ったザックを購入したのがこれ。
女性用に設計されている。
背負ってみて山を歩き、体に合ったザックというものはこうも快適なものなのかと驚いた。
それまでは特に気にせず、半額セールだからという理由だったり、ヤフオクで安く買えたからという理由だったりで、つまりザックにさほどこだわりを持っていなかったのだ。
容量は30L+5L。
2気室設計ではあるが、一気室にして使用している。
開閉方式はスタンダードなトップローディング式なので、荷物が増えてもわりと対応できる。
その一方でこのスタンダードな開閉方式は、巾着を締めて、さらに天蓋を閉じてという手間がかかる。
サイドにファスナーがあればなあと、せっかちなわたしは思うのだった。
だが天蓋の収納は使いやすいし、ウエストベルトの収納も容量を拡張できるのでかなり使い勝手が良い。
バックル(留め具)の開け閉めもスムーズ。
このバックルの設計がいい加減だと、これがかなりストレスになる。
有名ブランドでも、なかにはこのバックルがスムーズではないものもあるのでぜひ店頭で確認してほしい。
ミレーのサースフェーは、スタンダードなデザインでトンがった部分はないのだが、私としてははじめてのザックとしてもかなりおすすめ。
mont-bell:ALTIPLANO OACK40

1kgを切る重さ。とことん軽いザックに興味を持って購入。
 |
 |
このザックはロールトップとなっているが、別売りで天蓋もある。
ロールトップは開閉がとにかくラク。
このモデルは防水性がウリで、ザックには雨水を通しにくいインナーが入る二重構造になっている。(完全防水ではない)
防水性を高めるため、ファスナーなどはない一気室。
ショルダーベルトとウエストベルトに、小物収納のポケットがあって使い勝手も良い。
軽量化のためフレーム構造がないので、パッキング次第では背中に当たる荷物が気になることも。
わたしはこのザックは、霧雨や小雨のときなどレインカバーをかけるほどではないが、カバーをかけないとじわじわとザックの中身が濡れそうな天気の山行時に使っている。
天候を選ばなない点と、小物収納が使いやすい点が気に入っている。
バックル(留め具)もスムーズ。
MAMMUT:トリオン 38L
| ロールトップ。てっぺんで留めたとき↓
|
ロールトップ。側面でも留められスマートな印象に。
|
| 側面のファスナーからも本体荷物の出し入れ可能
|
天蓋は取り外し可能。
|
シュッとしたシルエットのザックが欲しかったのと、ロールトップで開け閉めラクなザックが欲しかったので購入してみた。
サイズは38Lサイズ。
フレーム構造がありながらも軽い設計。
側面にファスナーがあり、トップを開けなくても本体の荷物にアプローチできる。
ウエストベルトは取り外しができるので、ハーネスをつけるときなどは便利だ。
今はモデルチェンジになっているので、諸々改良されたと思うのだが、気になった点が2点。
・生地の撥水性が低い。
・バックルがすんなりと挿入できず途中でひっかかりやすい。
もうモデルチェンジになっているので、これら改良されていればいいな。


















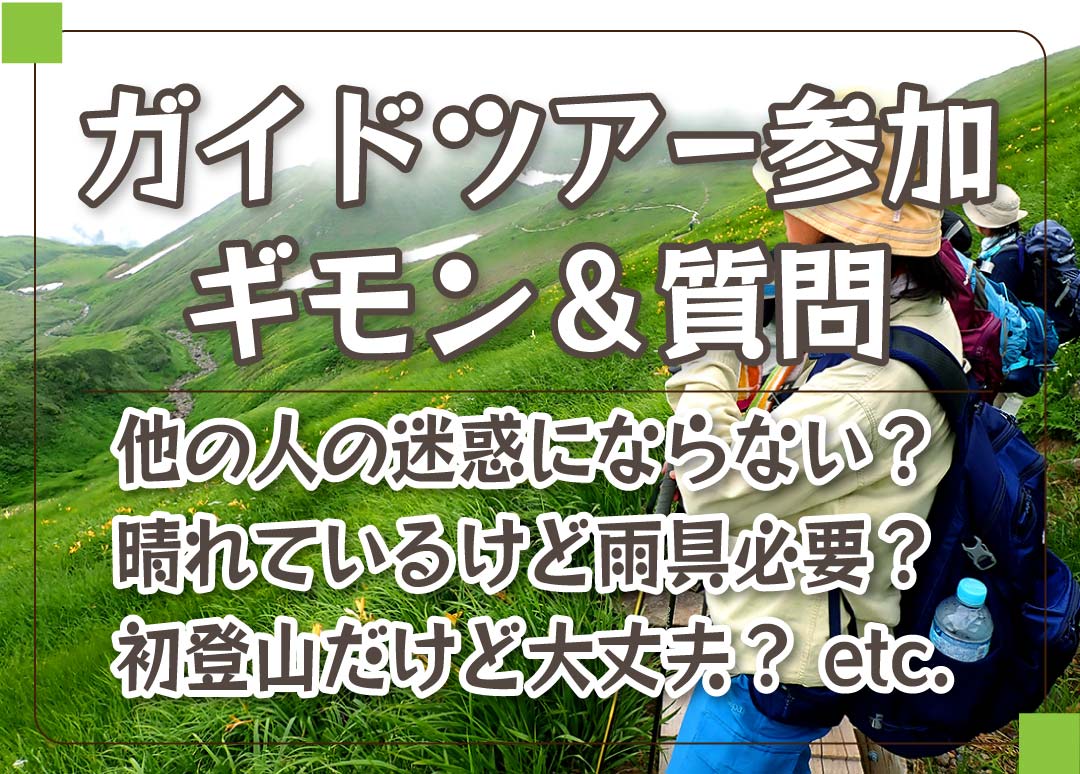

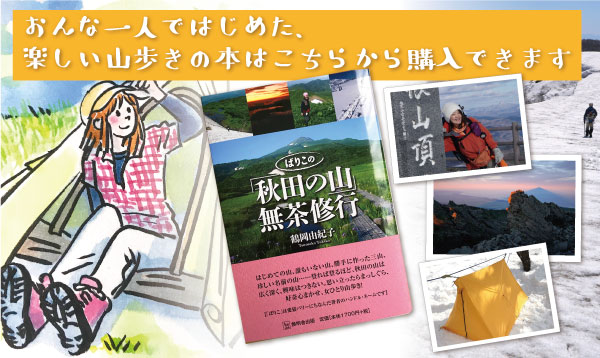
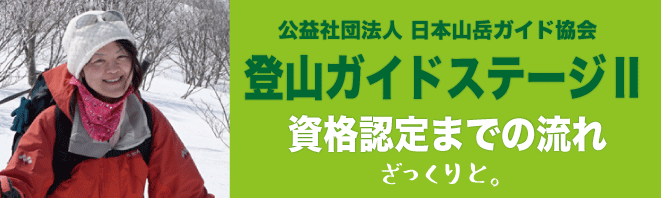



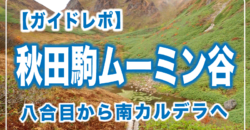

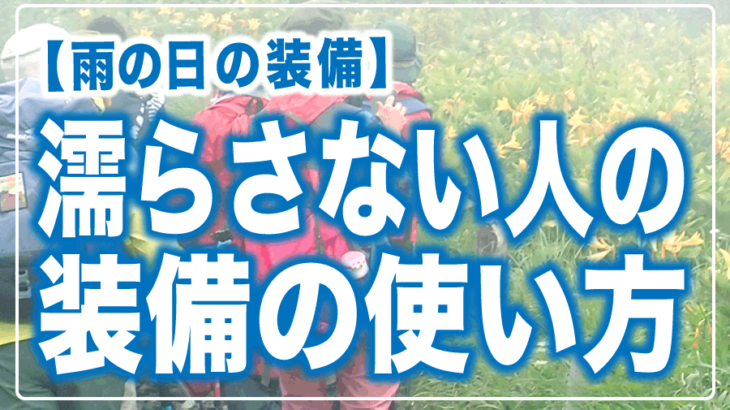

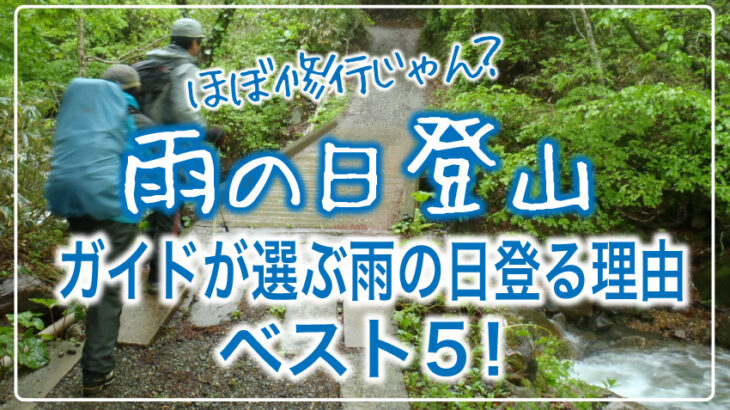


コメントを書く