
かねてから気になっていた、須金岳へ
この土曜日に登ってきた。
標高1253m。山頂に至る夏道はなく、
その手前の夏道上に仮の「須金岳山頂」が
あるようだが、それではなんだか
モヤモヤが残りそう。
なので雪のある今なら、ばりっと
山頂に立てるだろうと、目論んだ。
須金岳は鬼首カルデラの外輪山でもある。
山頂からはきっと、このカルデラが
一望できることだろう。
↓地形図はクリックすると
大きな地図が開きます。
ファイルサイズは500kb弱ぐらい。

コースタイム========
07:26 通行止めポイント
07:54 林道終点 登山道入口
08:30 水沢森の尾根に乗る
08:47 3合目
10:22 水沢森山頂付近
11:00 八合目
11:25 九合目
11:31 主稜線
12:15 P1241
12:30 須金岳山頂
12:55 下山開始
16:00 下山完了

須金岳の登山コースは大森平を起点とし
水沢森から途中、湿原を経て山頂に至るものと
寒湯沢橋付近から山頂に至るコースがある。
寒湯が最短コースで、仮山頂の九合目まで
3時間足らずのようだが、
前日、この登山口を偵察してみたところ、
林業の作業が行われていて
駐車スペースがなかった。
さらには、登山口の渡渉点には橋はなく、
雪解け水で沢も増水していたので
ここは諦めて大森平から登ることとした。

大森平登山口は、
通行止めとなっている旧国道の手前に
駐車スペースがある。
通行止めの柵を抜けて、歩いていく。

貯水池脇をすぎればすぐに
登山口を示す標柱が現れる。
ここから30分ほど林道歩きとなる。

林道歩きは正直つまらないが
本日は春紅葉が見頃なうえに
脇にはエンゴサクとカタクリ、
キクザキイチゲが出迎えてくれ、
退屈せずに済んだ。
ありがとう春の妖精たち。

林道で橋を渡るとまもなく、登山道が現れる。

しばらくは杉林を抜けていく。

まもなく、杉を抜けるとしばらく
巻道となる。この巻道が、急な斜面にあり
そのはるか下には小滝のある沢があり
なのに、落ち葉で足場も滑りやすく
思ったより緊張した。

登山道の標柱。
クマがだいぶ頑張った跡がある。

小沢があるのだが、
この辺りがやや分かりにくい。
沢を挟んでむかって左側が
登山道だ。

水沢森からの枝尾根に上がるまで
150mほど急登が続く。
途中の痩せ尾根に並ぶブナとミズナラ。

見た目、写真ではなだらかに見えるが
結構、きつい登りである。
それでも青空と新緑が美しく
気持ちは前向きだ。

尾根が近づいてくる。
今朝は明け方は車のフロントガラスが
凍るほど冷えたが、徐々に暑くなってきた。

尾根に上がって一休み。
痩せた尾根だが巨木が多い。
ウグイスのさえずりと、ときおり
ポポーポポーとツツドリの長閑な声。
ちなみにツツドリはウグイスの巣に托卵する。

山桜は満開で、その奥には
真っ白な片倉森1040m。
三角点あり、登山道なし。

稜線上には今にも歩き出しそうな
ブナがいた。
着いて来られたらどうしようか。
なんと、イワウチワが咲きそろっていた。
ちょうど見頃で、しかも尾根上を
えんえんとイワウチワ街道が続く。
もう今年は見れないつもりだったのに
思いがけないサプライズだ。

地味ながらもコヨウラクツツジも
咲いております。

尾根にはクロベとゴヨウマツも
登場。
どれも見ごたえのある巨木である。

3合目。
2合目の標柱もあるのだが朽ちていて
登りでは気がつかなかった。

梢の向こうに見えてくるのは
須金岳の主稜線上にあるP1191。
その奥にP1241。
気持ち、その奥に真っ白な須金岳山頂が
見えなくもないような。。。

キタコブシも咲いたばかり。

9時、四合目。

環境が厳しいせいか、
奇妙な造形の巨木が多い。
思わず座りたくなるような枝ぶりのブナ。

そしてこちらはクマ棚だな。

ブナが根っこから倒れていた。
まだ生きているから、起こしてあげたいものだ。

それにしてもあの巨木が地中に
せいぜい30〜40センチほどの深さに
根を張って生きていたのかと思うと
驚いてしまう。

分岐。
分岐のブナの幹には
「ホドウ」と書かれてある。
地形図では750mの標高に道があるが
今現在、道は650m付近から伸びてある。

3頭のミズナラの木。

三合目を過ぎたあたりでは
遠く感じた1191のピークがだいぶ
近づいたように見える。

写真じゃのどかな緩斜面に見えるが
結構きつい。

750m付近は平坦な地形がしばらく続く。
森の向こうに見えるのが
水沢森の山頂だ。

760mぐらいから再び急登に。
水沢森まで200m以上、この急登が続く。
800mあたりから雪が出てきた。

p1191までの稜線は雪がない様子。

水沢森の山腹は気持ちのいいブナの疎林で、
芽吹き前のためもあり、空は明るく
清々しい場所だった。
伐採後の二次林の若い森などでは
まだ生存競争の真っ只中で
細いブナがまさに林立する。
しかし、
ここまで成熟した森となれば、
巨木が広げる葉で日光が遮られ、
若い木はなかなか大きく育つことができず
こんな広々とした景色になるのだそうだ。

成熟したブナ林は実に豊か。
朽ちた老木には菌や虫が入り、さらに
虫を狙うキツツキの餌場にもなり、
静かにゆっくりと
他の生命に取り込まれてゆく。

すがすがしい森に急登も忘れて
登っていくと、なんだか山頂の様子がヘン。

山頂には巨大な雪庇が崩落したあとの
雪壁がそそり立っていた。
高さ3メートル以上はある。
そしてほどんどがハングしている。
どこか低くなっていないかと見渡したが
結局この雪壁をアイゼンとピッケルで
乗り越えることにした。
あいにくこの日に限って
わたしは10本爪の前歯のない軽アイゼン。
そして昨日の金峰山には背負っていった
ザイルを今日は持ってきていない。
スリングが120と60。
T中氏が180と120。
背後は滑落したら止まりそうにない斜度で
谷となっている。

12本爪アイゼンのT中氏が、
わたしのピッケルとじぶんのピッケルで
ダブルアックスで雪壁を登り、
そこでアンカーをとったら、
あるだけのスリングを連結させて
わたしを確保。
確保されながら、雪壁を登り切る。

たまにはこういう
スパイスの効いた展開もいいものだ。
雪壁に登ると絶景。後ろを振り返る。

行く手を見渡す。
いったん、水沢森から30mばかり下り
そこから主稜線へ200m、登っていく。
登りきった稜線の上は
地図によれば天狗の角力取り場と呼ばれ
小湿原が広がるようだ。
もっとも、今日は雪原となっているのだろう。
そして鬼首のカルデラや
虎毛山、ひょっとすれば万滝も
見られるかもしれない。

雪庇跡を過ぎると、もう雪がなく
さっき履いたばかりのアイゼンをもう
脱いで夏道を行く。
冬から再び早春に景色が戻った。
〜〜〜絶景が待つ後編へ続きます〜〜〜



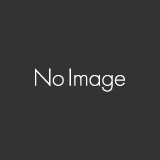
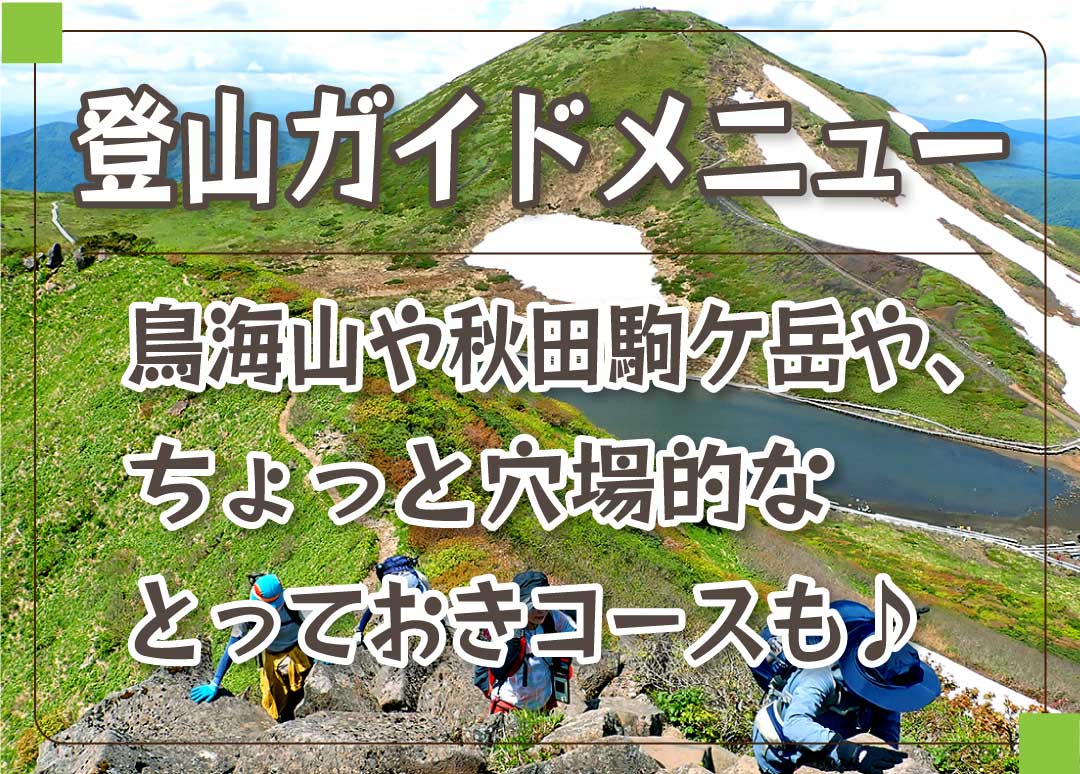
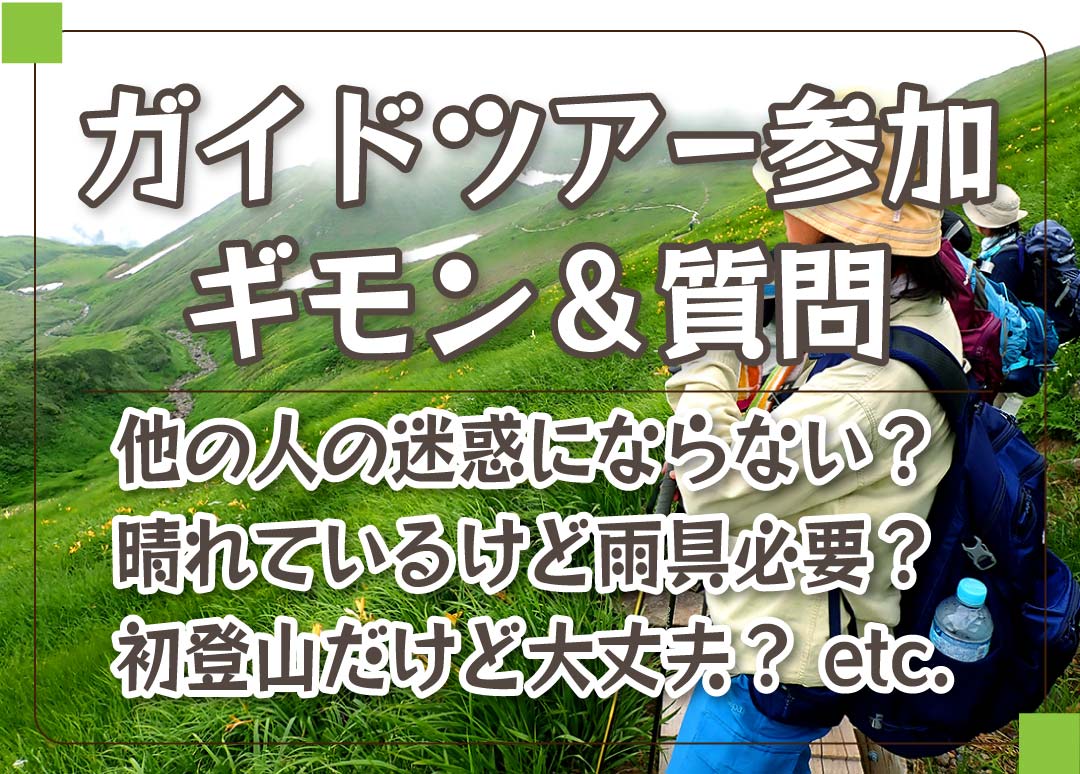

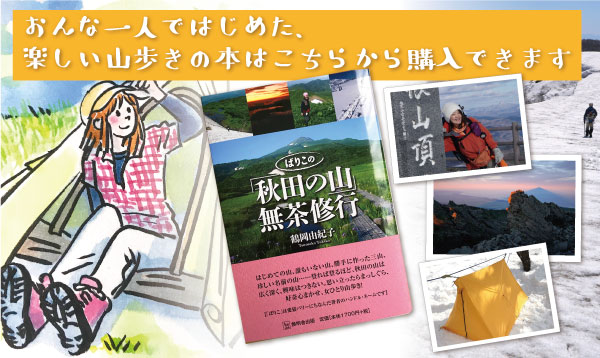
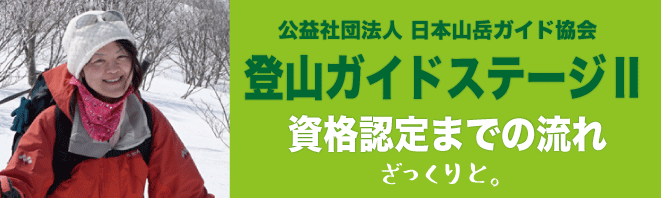



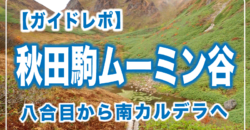



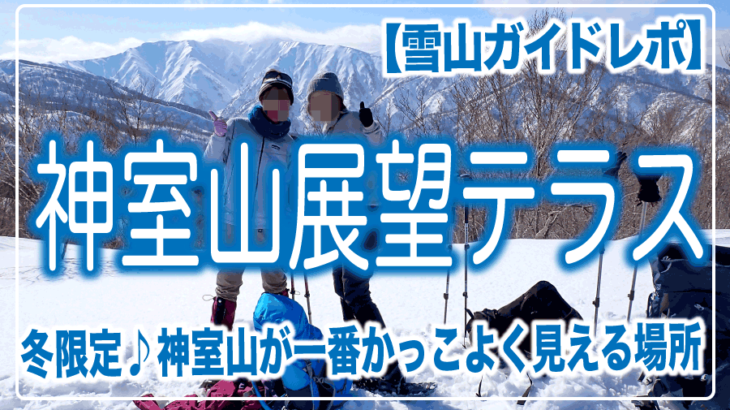
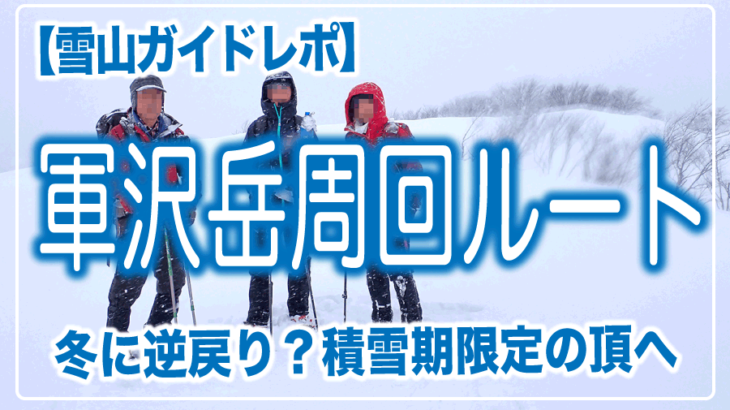
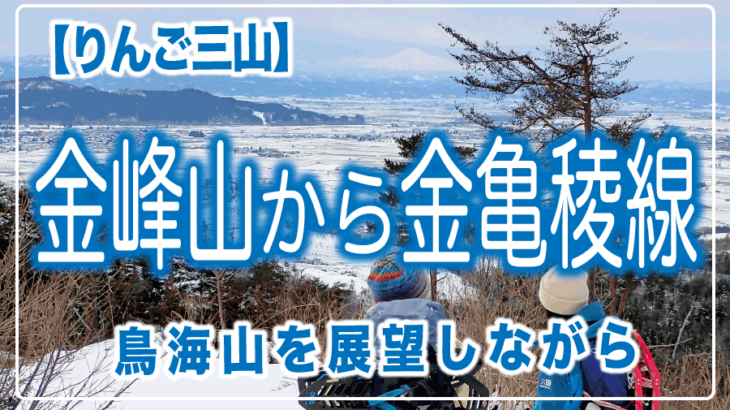

[…] 〜〜〜須金岳前編はこちらです〜〜〜 […]