
和賀山塊の北に位置する羽後朝日岳は標高1376m。
秋田や岩手の山屋にとっては、
憧れの一座のひとつではないだろうか。
というのも、この山、かつてはヤマケイの
分県ガイドにも記載があったが、
いまでは一般登山道がない。
もっともポピュラーなルートは、岩手の沢内から
沢尻岳、大荒沢岳の稜線を伝って至るルート。
ただし、大荒沢岳から羽後朝日までの稜線は
灌木帯の藪となる。
なのでこのルート、雪があることが前提。
和賀山塊の主峰、和賀岳が男前なのに対し
羽後朝日岳にはどこか貴婦人のような
印象がある。
その奥羽の貴婦人を5年ぶりに訪ねたくなった。
5年前のテント泊山行はこちら
◇コースタイム(休憩込)
07:00 貝沢集落そばの駐車スペース出発
07:25 登山口の標柱着
08:29 P770
09:40 P1091
10:30 沢尻岳
11:14 大荒沢岳
11:50 羽後朝日岳
12:20 下山開始
15:30 登山口
16:00 駐車スペース
◇駐車スペースと登山口までの林道歩き

惚れた山にはどうしても
ひとりで登りたい。ということで
羽後朝日岳、本日は単独山行だ。
7時少し前に駐車スペースに到着。貝沢の集落から
ほんの少し進んだ、林の入り口にある。
ひょっとしたらもっと先まで行けるかと
期待していたが、すでにこれだけのクルマが
ここにあるとすれば、この先はまだ雪が
あるのだろうなと、わたしもここで身支度をし7時ごろ、出発。

先週の神室の役内口までの林道歩きの距離よりは
かなり短いから気楽ではある。
林道脇にはミズバショウやキクザキイチゲが咲き
しかも、残雪はほんの一箇所だけで
車高の高い車なら難なく突破できそうだった。

うん。残雪突破した車が数台あった。
この先も行けそうだが、カラマツの枝が
散乱してたりでやっぱり
車高の高い車でなければ躊躇しちゃうかも。
さらにこの先、「登山口→」の看板の手前に
スペースがあるが、このスペースを駐車に
使っていいのかどうか不明だった。

渡渉点の手前の林道のみ、残雪がかなりあった。
ここは車はきびしいかも。

渡渉点。
朝の水量はこんな感じ。下山のときには
雪解けが進んだらしく水量がもっと増えていた。
ゴアの靴にスパッツをつけていれば
浸水することなく通過できる程度。

7時25分、登山口看板到着。
ここまでの道すがら、展望できる白い頂は
モッコ岳。
◇登山口からとりあえず沢尻岳をめざす

登山口から10分から15分ほどで
尾根の取付きとなる。
国土地理院の地形図に記された登山道より
もっと手前の尾根に登山道はある。

尾根取り付きから杉林を抜けるとまもなく
痩せ尾根の急登となりクロベの
巨木が現れる。
この先150mぐらいは修行モードで
もくもくと急登を行く。

イワウチワはほとんどつぼみだったが
ちらほらと咲き始めていた。

そしておなじみ「どすこいの木」。
わたしが勝手にそう呼んでいるだけ。

登山道には徐々に雪が現れる。
ほどほどに腐れ、ほどほどに締まっていて
ツボ足で十分だった。

P770が見えてきた。
ここでいくつかの尾根が収束する。
つまり下山時にはどの尾根を下りるか
ルートファインディングが必要となる。
念の為、ピンクテープを結んでおいた。

8時30分、ナントカ分岐。看板はもはや判読不能だ。
新郡界分岐、とかつては記されていた。
P770の緩やかな雪面を楽しんだのち、
この尾根から再び急登。200mほどをもくもくと。

8時50分ごろ、前山分岐が見えてきた。
5年前、一泊テント泊で
羽後朝日を目指したときは
あの尾根を使って、スキーで登ったっけ。

前山分岐。
このあたりはなだらかな斜面にブナの森が
広がっていて気持ちがいい。

モッコが近づいてくる。
さて本日、羽後朝日に行けるかどうか、
沢尻岳到着が10時30分なら羽後朝日、
それを過ぎたら、モッコにしようかと考えている。

前山分岐を過ぎるとルートは北西向きに。
ぐんと見晴らしが良くなるし、
なにより鬼の急登もここまで。

この稜線の景色として
やたら存在感のあるあのモッコは沢尻岳から
北東へ派生する尾根上にあるピーク。
羽後朝日岳や和賀岳の絶好の展望地。

沢尻岳も見えてくる。
さらにその奥には大荒沢岳。

夏道脇の雪を渡れるかと思ったが
今日の気温と雪の状態からしてむり。
露出した夏道を使う。

いつも迫力の雪庇崩壊を見せてくれるポイント。
もちろん、この先は樹林帯に逃げる。

樹林帯は笹がだいぶ出ているが、
夏道は出ていなかった。

矮性のブナが森を作るも、
だいぶ生育しずらいらしく、苦悶の枝ぶり。

樹林帯を抜けると沢尻岳の緩やかなピーク。

上空には巻雲。晴天が続く兆し。

10時30分前に沢尻岳到着。
本日は、マイナー山域らしからぬ
多くの入山者がいるが、みな早い時間に
出発したようで、わりと静かな山域を楽しむ。
沢尻岳ではひとり、男性が気持ちよさそうに
昼寝しているだけ。
◇晴天にさそわれ羽後朝日を目指す

予定通り、羽後朝日方面へ向かうことに。
とりあえず、大荒沢岳まで行って
藪の露出次第で貴婦人の元へいくかどうか
考えるとする。

沢尻岳から先は、アップダウン。
なんてったって大荒沢岳まで登って、
下ってからまた登り返しての羽後朝日。
大荒沢岳が途方もなく大きく見える。

沢尻岳付近でも展望は申し分ない。
あちらに見えるは秋田駒ケ岳。
当然、岩手山も、森吉山もくっきりだ。

大荒沢岳の手前の小ピーク。
途中で下山してくる男性と挨拶。
聞けば大荒沢岳からは和賀岳の奥に鳥海山が
くっきりと展望できて、もうそれで
満足して戻ってきたという。
いっそわたしも大荒沢岳でのんびりと
雄大な展望をながめてランチタイムだけでも
いいかもなと、かなり軸がぶれるのだった。

11時10分、大荒沢岳。手前の黒い丸。
これがたぶん標柱かなにかの頭の部分だ。
5年前は4月27日に登ったが、当時は
山頂は藪が出ていた。
今年はずいぶん雪が残っている。

大荒沢岳から右手に和賀岳。さらにその奥に
鳥海山。
大荒沢岳直下の登りで、大音響で
ヒップホップをかけて降りてくるバカ者、
あ、いや、ワカ者がいた。
こんなバカといや、ワカ者と
山頂を共にしなくてよかったとほっとする。
さすがにあまりの音響だったので
「うるさいよ!!!」
と言ってやったが、意に介する様子もなく
ニヤニヤしたまま下山していった。
ひょっとしたらイヤホンしているつもりが
はずれていたのかもしれないが、
・・・理解に苦しむ。
そういえば昨年の夏、鳥海山の山頂で
中島みゆきを聴いていた若者がいたっけ。
こういう人たちは、何をもとめて山に入るのか。
下界で聴いときゃいいだろうし
ひとりで聴けばいい。

ま、そんなシーンもありましたが
嫌なことは忘れてお釣りがくるほどに本日は
素晴らしい展望!
秋田駒から岩手山、ちょこっと鞍掛山までの
スカイラインといったら!

羽後朝日方面から来た3人グループに
行こうかどうしようか迷ってるといったら
いや、きょうは行った方がいい!
昼前には行けるし!と熱く推され
そうだよなと、羽後朝日へ向かう。

5年前は藪が出ていて、
結構難儀した大荒沢岳からの下りも
今年は十分に雪がある。

大荒沢岳を振り返ると
巨大なサルノコシカケのような雪庇。

遠いようで、割と近い。
あれが羽後朝日岳の山頂だ。
遅い時間出発したおかげで独り占めできそう。

山頂直下最後の登り!

12時前に到着できた!
田沢湖が外輪山に縁取られてくっきりと。
その奥には森吉山。太平山地も白子森から奥岳の
稜線がくっきりだ。

山頂からあちらが、武将「和賀岳」。
奥に控えるは鳥海山。

志度内畚手前の名もなき稜線は
生保内側の源流を抱き込んで、屏風のように
急峻な壁を作る。

風もなく、おだやかな山頂を独り占めしていると
じぶんが最後の入山者かと思っていたら
3人グループが登ってくるのがみえた。
山頂を交代して下山することに。

羽後朝日と大荒沢岳のコルから眺める和賀岳。
深い谷の奥に鎮座するその様子は
もう惚れる!ここからの眺めがなかなか。

そしてコルから少し登り返しての
大荒沢岳。
通過するだけのピークだが
なかなかかっこいいではないか。
きょうの日差しは、さながら腕のいい照明係で
どの山もすこぶるかっこいい。

大荒沢岳と手前の樹木。
きょうの晴天の清々しさにうかれ、
どうでもいい写真をたくさん撮るのだった。

沢尻岳を降りて、元来た道を帰る。
ここまでおりてくれば
あとは樹林帯になってしまうので
一休みすることに。

山のコーヒーはなぜにこんなにうまいのか!
コメダの羊羹をお供に。

15時30分、登山口到着。
ここからは30分ほど、今夜のおかずを
採りながら林道歩き。

下山の途中で見つけたイワウチワの白花。

エンレイソウも今年のお初。








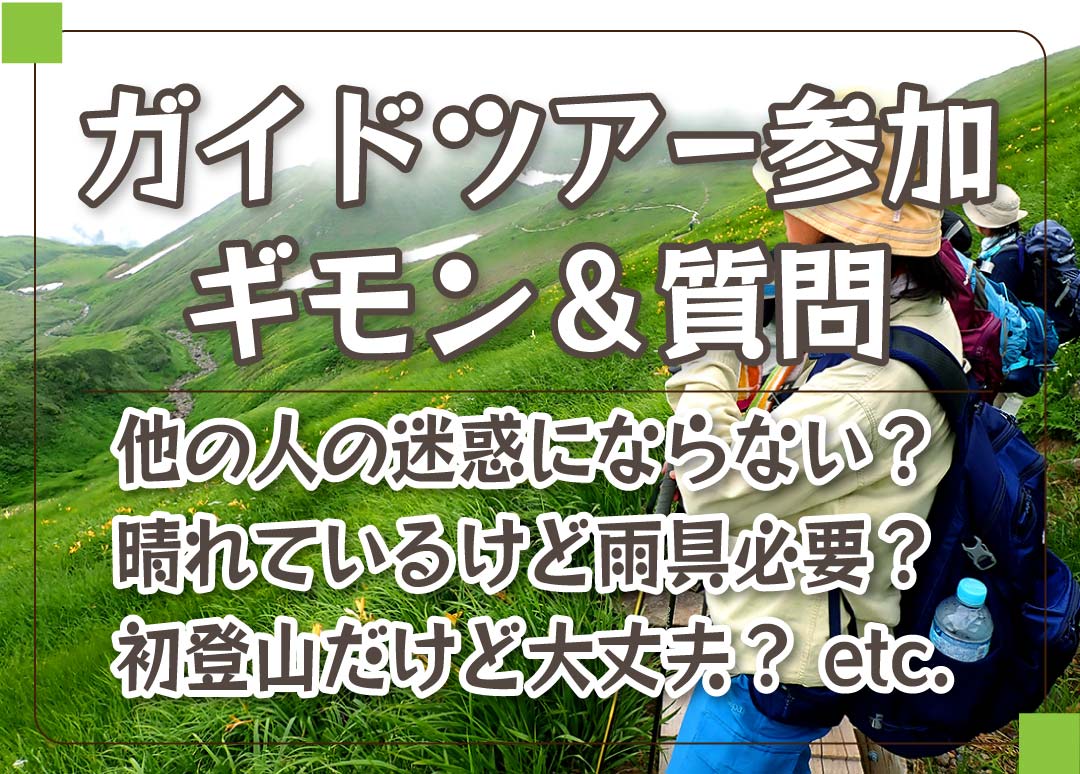

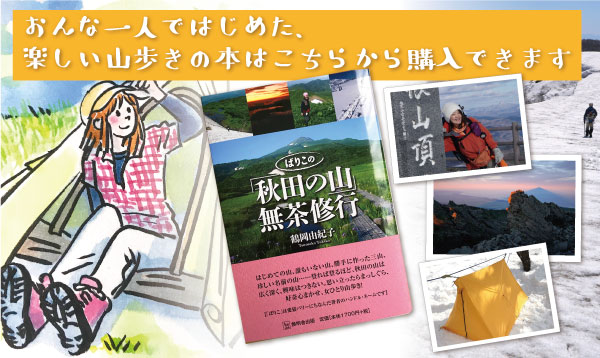
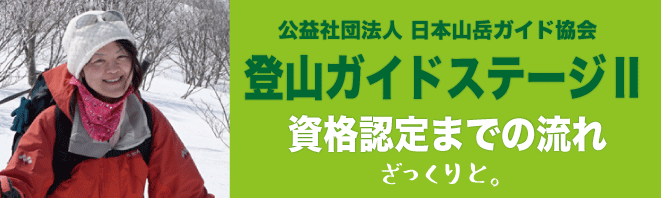



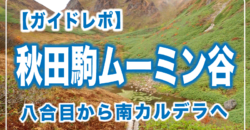



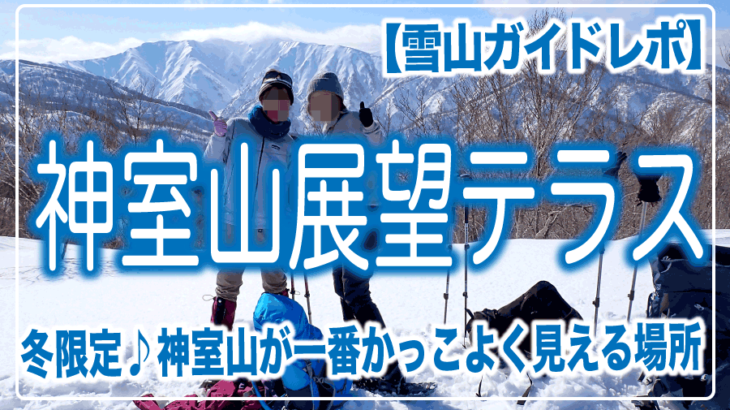
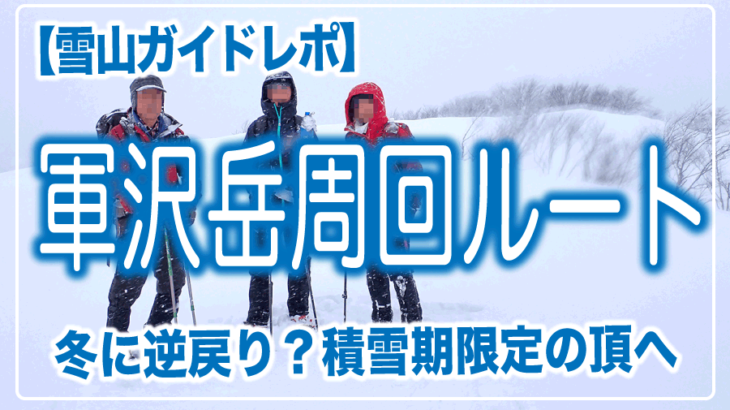
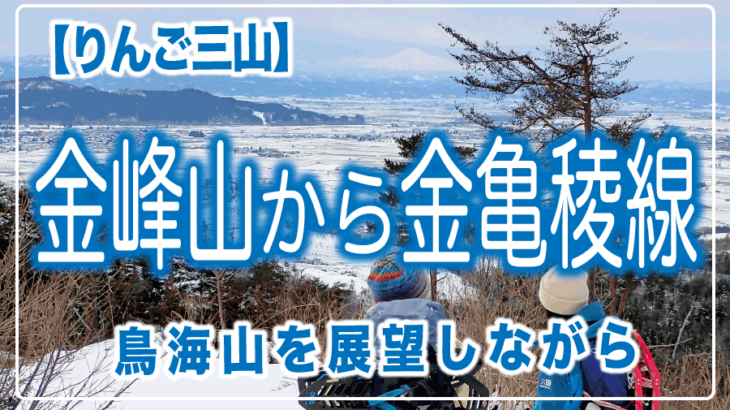

コメントを書く